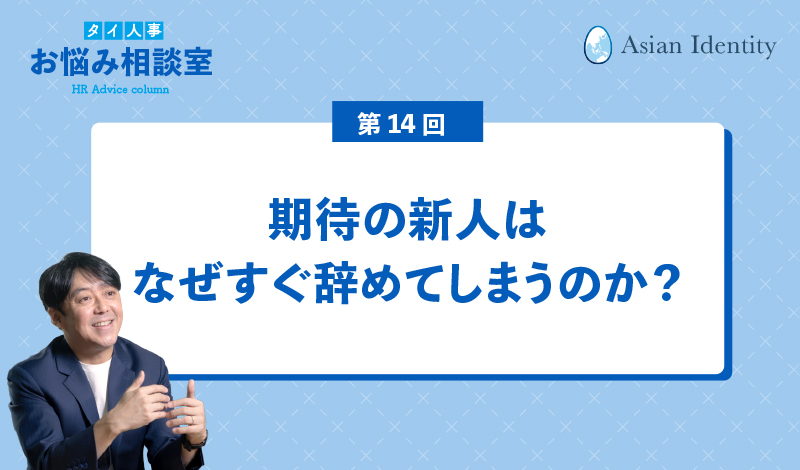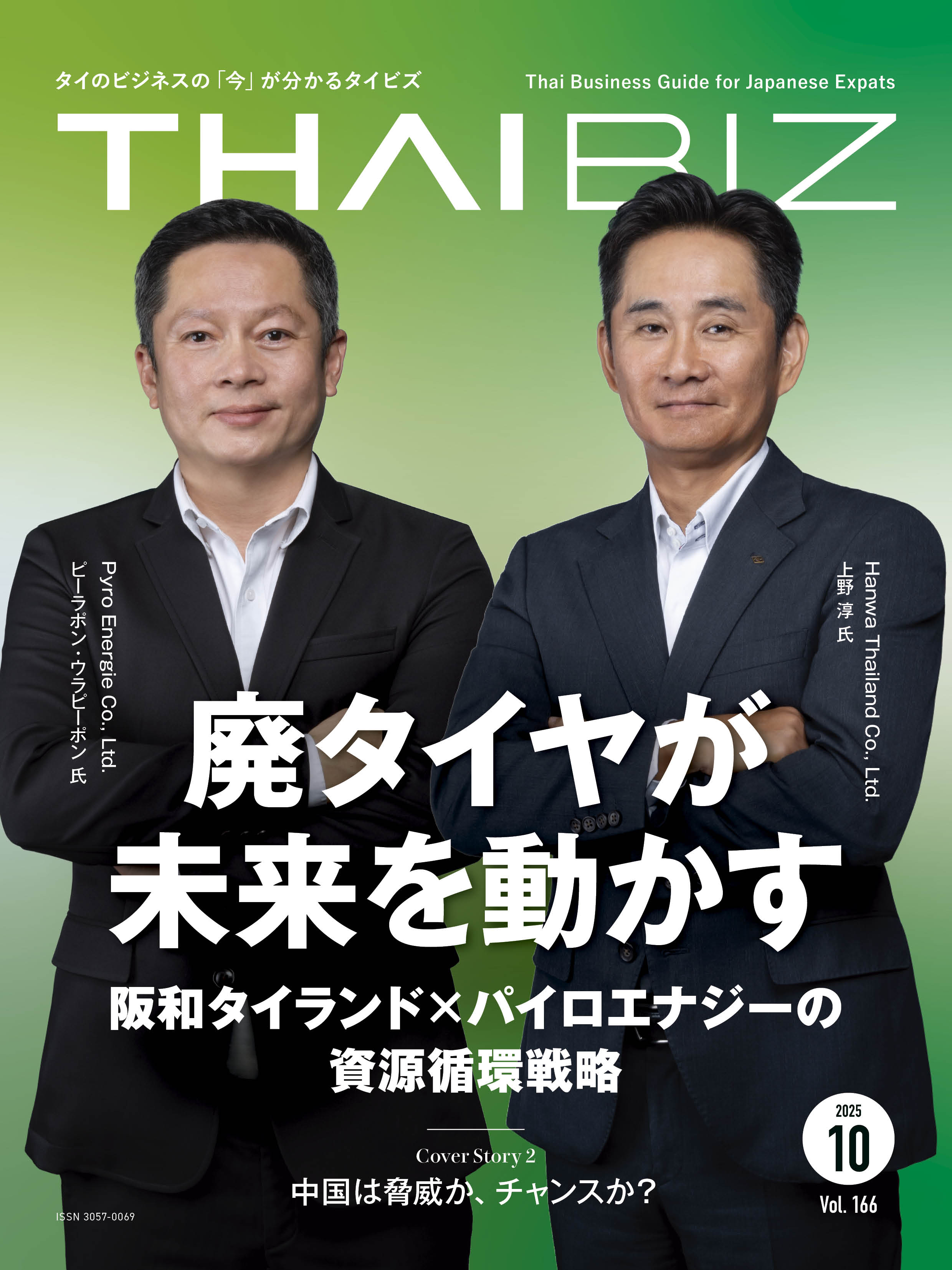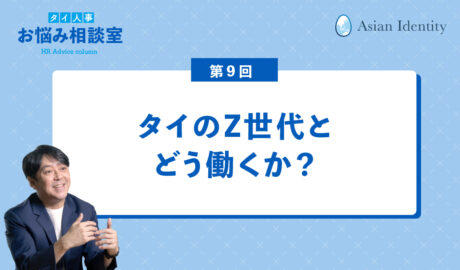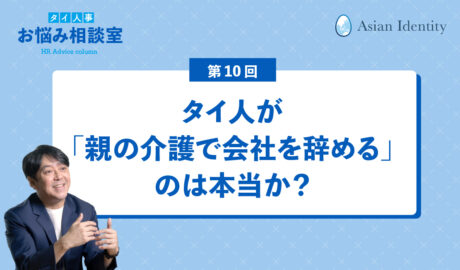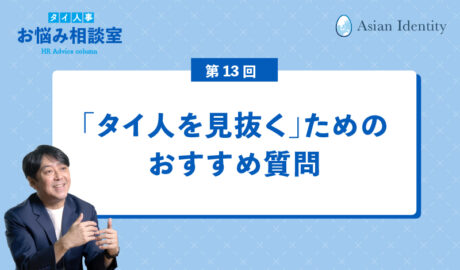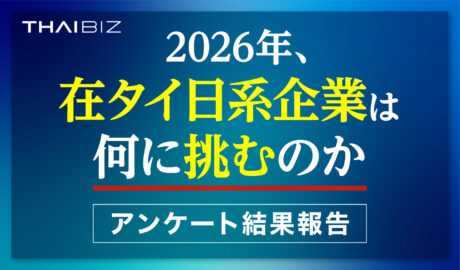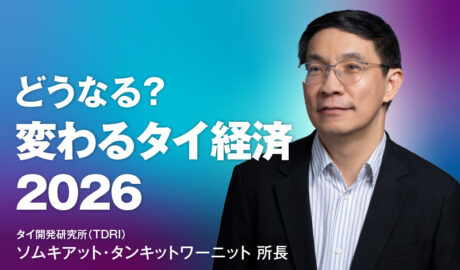THAIBIZ No.166 2025年10月発行廃タイヤが未来を動かす ー 阪和タイランド×パイロエナジーの資源循環戦略
この記事の掲載号をPDFでダウンロード
最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中
期待の新人はなぜすぐ辞めてしまうのか?
公開日 2025.10.10
Question:せっかく採った優秀なタイ人スタッフがすぐに退職してしまいました。再発防止をどのようにしたらよいでしょうか? Answer:スキルだけではなく「態度」を見ることが必要です。
今回も、前回に続き「採用」がテーマです。なかでも、何が採用の成否を分けるのか、入社後のミスマッチをどうしたら防げるのか、という点について考えてみます。
言葉は飾れても表情は嘘をつけない 採用のミスマッチを防ぐために、私が面接官として大切にしているのは「答えの内容」だけでなく、「答え方」に目を向けることです。なぜなら、「答え方」にこそ人の本質が現れるからです。
心理学の世界に、ポール・エクマンという著名な研究者がいます。彼は人間の顔に現れる「微表情」という概念を提唱しました。これは、言葉では取り繕えても、感情が一瞬だけ顔に出てしまうという現象です。特に「怒り」や「嫌悪」といった感情は、抑えていても表情や動作に小さなサインを残します。
例えば、「なぜ前職を辞めたのですか」という質問を突っ込んでいくとします。最初は前向きなことを答えていても、退職というのはネガティブな事情も何らかあるはずです。こちらとしてはそうしたところの本音を探りたいのです。核心をついていくと、微笑みながら答えた候補者が、眉間にしわを寄せるような表情を一瞬だけ見せることがあります。
こうしたサインは、言葉の奥にあるその人の本質を探るヒントになります。もちろん、これらの反応だけで「自分を偽っている」と決めつけることはできません。しかし、「何か違和感がある」と感じたときはその感覚を大切にし、そこからさらに掘り下げてみることが有効です。
また、採用面接では「苦しかった経験」や「失敗体験」を聞くことが重要です。入社後に訪れるであろう困難を乗り越えられるかをわれわれは知りたいからです。逆に、成功体験からはその人の本質はなかなか見えません。「苦しい体験」の話題を深堀ったときに見せるその人の表情、それが入社後に見せる表情です。
話を具体的に掘り下げていくことができると、相手の感情はその「場面」を経験していたときの感情に近づいていきます。話しながらネガティブ感情を顔に出してしまったり、あるいはストレスのかかったような話し方をしたりするのであれば、もしかしたらプレッシャーに弱いタイプかもしれません。
反対に苦しい状況の話を、冷静にとらえ直した表情で話すことができたら、セルフコントロール力が高い候補者と言えるかもしれません。
ただし一点、日本とタイで異なる点として注意したいのは「笑み」の意味が異なるということです。タイは微笑みの国というだけあって、照れ隠しの笑顔、怒りを抑える笑顔など、タイ人はさまざまな場面で「笑み」を使います。しかし、こうした笑みを見せる場面でも、目は嘘をつけません。口元ではなく目の周りに注目をすることでその人の本音をうかがい知ることができます。
面接官として採用判断を間違えないためには、特に「表情」を見るというのが重要なスキルなのです。こうした訓練をほとんどの人は受けていませんが、普段面接の機会がある方であれば、表情を意識することにトライしてみてください。経験値が上がるとだんだん感覚が身についてきます。
「人物像の定義」がないと面接の精度は上がらない 「やっぱり面接は難しい」。そう感じる面接官も少なくないでしょう。まさにその通りで、日常的に話す機会がある部下とのコミュニケーションや評価ですら簡単ではないのに、面接は初対面の方との一発勝負です。限られた時間の中で成果を出すことは決して簡単ではありません。
加えて難しいのは、「採用はチーム戦である」 ということです。一般的に採用選考というのは複数人の目を通します。その際に「人によって基準が違う」ことがしばしばあり、それが選考プロセスをより難しくします。
自分は良いと思ったのにタイ人HRは良くないと言う、あるいはその逆もあるでしょう。ある面接官は「人柄重視」、別の面接官は「即戦力重視」、また別の人は「雰囲気でなんとなく」選んでいる。そんな状態では、いくら丁寧に面接をしても、判断の軸がばらつき、入社後のミスマッチにつながりやすくなってしまいます。面接官によって見るポイントがバラバラでは、組織としての判断もぶれてしまうのです。
ここからわかることは、面接官個々の「面接スキル」だけでなく、「選考プロセスの標準化」を組織として設計しておかないと採用の成功はおぼつかないという事実です。特に「どういう人が欲しいのか」という求める人物像の定義が必要になります。
タイ組織での成果を左右する「態度」と「ソフトスキル」 一般に、人材の要件を整理する際は「KSA」という枠組みが用いられることがあります。これは Knowledge(知識)、Skill(スキル)、Attitude(態度)の3つを意味します。
タイでの採用面接で最も重視されやすいのは直接的に業務に関係する「知識」、そして資格や語学能力などの「ハードスキル」ではないでしょうか。経理経験が10年以上あり、日本語ができるなどの基準で候補者をわれわれはまず洗い出します。
一方で、見逃されがちなのがAttitude(態度) 、あるいは「ソフトスキル」 です。タイにおけるミスマッチの原因の多くは「組織になじめなかった」という理由です。タイの組織では「内集団」(=仲間)に入れるかどうかでパフォーマンスが大きく変わります。
いくら経歴が良くて目立ったスキルを持っていても、組織に溶け込めないと「仲間外れ」のような状態が起きてしまうことが少なくありません。ですから、どういう態度を持っているのか、また周囲と双方向のコミュニケーションが取れるのか、という点をよく見ておかなくてはなりません。
特に、ハードスキルは後から身につけることができますが、価値観や姿勢といった“人となり”(ソフトスキル)はそう簡単には変わりません。
履歴書に書かれている表面上のスペックの高さだけで採用してしまい、人間性を見落としてしまう。その結果チームに馴染めず、結果的に早期離職してしまう。そういう例が非常に多いのです。
「態度」は理念や行動指針から落とし込む
では、「態度」や「ソフトスキル」を面接の基準にするためにはどうしたらよいのでしょうか。「嘘をつかない人」「明るい人」など、一般的な人間性も基準になりますが、やや当たり前すぎてしまいます。おすすめは、自社の理念や行動指針 をもとに、「自社らしい」言葉を定義することです。
例えば弊社では「Self-Starting(自律的に動ける)」という姿勢を重視しています。小規模の会社なので指示待ちでは困るということ、またコンサルタントというプロフェッショナルな職業なので高い自発性を持ってほしい、といったワーディングを指針として定義し、社内の評価基準にも組み込むとともに、選考段階から見るようタイ人HRと認識を合わせています。
できれば、基準を元に具体的な質問例にしておくこともおすすめです。「求める人材像」→「採用基準」→「それを見るための質問」ということを整合させることで、「この人はうちの文化に合うかどうか」をチームとしてチェックすることができるのです。以上、今回はタイでの採用のミスマッチを防ぐための方策について考えてみました。
>>本連載「タイ人事お悩み相談室」の記事一覧はこちら