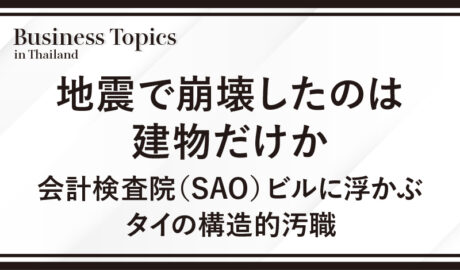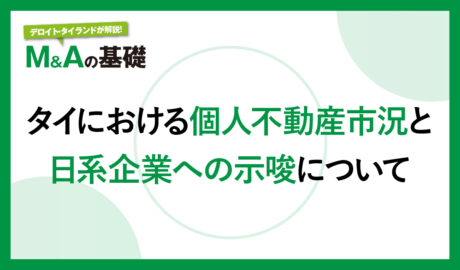THAIBIZ No.164 2025年8月発行在タイ日系製造業の変革 日新電機タイが変われた理由
この記事の掲載号をPDFでダウンロード
最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中
在タイ日系製造業の変革~日新電機タイが変われた理由
公開日 2025.08.08
タイ人キーパーソンが語る、組織が変われた理由
日新電機タイの飛躍には、タイ人社員の存在も欠かせなかった。生方氏が社長に就任した当初は「タイ人社員からの反発も大きかった」というが、そこからどのようにして彼らの協力を得て、組織の変革と成長を実現していったのか。その背景を、生方氏および、現場で組織を支えるタイ人キーパーソン3人に聞いた。

Q.生方氏が社長に着任してから、どのような変化があったか
キッチャヤー氏 私はこれまで27年間にわたり、日新電機タイのあらゆる姿を見てきましたが、以前は長らく変化に乏しい状態が続いていました。
そうした中で生方社長から、仕事の進め方やものづくりに対する考え方を学ぶことで、私たちの視野が広がり、初めて会社に変化の波が生まれました。今では、工場やオフィスの風景だけでなく、社員一人ひとりの業務に対する姿勢も大きく変わったと実感しています。
ウィライラット氏 以前の当社には家族的な一体感がありましたが、一方で、規律に対する意識やその実践が十分とは言えませんでした。生方社長は、挨拶の重要性から仕事の進め方に至るまで、規律の本質を私たちに示してくれました。
特に大きな変化として実感しているのは、私たちタイ人社員の「意識の変化」です。生方社長の就任後、毎週月曜日に幹部と次世代幹部候補が自部門の課題を全体共有する場が設けられました。
この時間には、他部門への依頼事項を直接伝えることができるだけでなく、部門横断的な改善提案なども交わされるようになりました。社員が無意識のうちに抱えていた“壁”が取り払われ、部門を越えた協力体制が生まれたのです。
また、現場でミスが起きた際も、従来は当事者への注意で済ませていたところを、生方社長は会社全体の課題として捉えました。
オフィスも含めた全部署の全リーダー以上約60名を集めてミスの内容の確認と対策立案までを現場で行い、各リーダーが自部門の部下全員に共有しています。全社をあげて再発防止策を徹底するという姿勢が根付きつつあります。
Q.変革に対して、反発の声は
生方氏 タイ人社員からの反発や拒否反応は、かなりありました。特に、半導体関連製品の売上が伸びていた時期に生産ラインの整備を試みた際には、「リスクが大きいのでやりません」と明確に反対されたこともあります。当時は私が就任して間もなく、まだ具体的な成果を出していない段階だったため、社員の間に不安があったのだと思います。
しかし、反発を受けながらも変革を推進し、小さな成功を積み重ねていくことで、徐々に社員の意識が変わり始めました。変化に対する抵抗感が薄れ、自発的に行動を起こす社員が出てきたのです。
例えば、オフィスの整理整頓を一人の社員が始めると、それを見た他の社員も追随し、職場環境が一気に改善されました。そして、その変化を目の当たりにした工場の技術者たちも、自ら課題を洗い出し、改善案を提案してくれるようになったのです。
キッサダー氏 現場からの反発に直面しても、生方社長は決して諦めることなく、常に明確な方針を示しながら、一つひとつの改革に込められた意義を根気強く説明してくれました。
「会社として持続的に成長するには、常に改善し変化し続けていく必要がある」という言葉を繰り返すだけでなく、自ら積極的に動くことで、変化の重要性を私たちに示してくれたのです。
私自身も、塗装部門のマネジャーから現在のポジションに突然異動した際、業務内容の大幅な変更に戸惑い、「自分に務まるのか」と大きなプレッシャーを感じていました。
しかしその時、生方社長から「変化を起こすには、まずは一歩踏み出すことが大切。最初から100点を目指す必要はない」と声をかけられたことで、気持ちが軽くなり、次第に自信を持てるようになりました。
Q.さまざまな理由から変化に踏み出せない日系企業に伝えたいことは
キッチャヤー氏 社会は常に変化しており、企業もその流れを見据えて柔軟に対応していく必要があります。タイ人と日本人が、お互いの価値観を尊重しながら、共に変化に向けて行動していくことが、これからの企業には欠かせない姿勢だと思います。
ウィライラット氏 「変えても意味がない」と最初から諦めてしまう人は少なくありません。しかし、たとえ小さなことでも“最初の一歩”を踏み出すことが極めて重要です。私たちは、自らの力で生き残る道を見出さなければなりません。そのためには「変化を恐れない勇気」、そして「挑戦する勇気」が不可欠だと考えています。
キッサダー氏 生方社長が着任してから、当社では同じ生産方式や工場レイアウトを長期間維持することは少なくなり、常に現場の状況に応じて変化を続けてきました。その過程で、私たちは内製化を徹底し、多くの知識や経験を蓄積してきました。
いま振り返って感じるのは、「現状維持」は一見安心に思えても、新たなチャンスを逃すリスクを伴っているということです。
変化に挑んで失敗することがあっても、そこから学び、再挑戦することは可能です。しかし、変化を避け続けていれば、自分たちが何を逃しているのかさえ気づけず、時代に取り残されてしまう恐れがあります。
Q.変革で重要なポイントは
生方氏 変革において、私が最も意識しているのはタイ人社員とのコミュニケーションです。特に大切にしているのは、現場を自分の目で見ること。
私は毎朝、就業前に工場を巡回し、良い改善があればその場で写真を撮り、実行した社員には直接声をかけて称賛します。その改善内容は幹部や次世代幹部候補が参加する会議でも共有し、「このような取り組みを見習ってほしい」と伝えています。
こうした行動が、「自分の努力が認められた」という実感を生み、社員の働きがいや生きがいにつながっているのだと思います。その積み重ねによって、今では世界の大手メーカーが来訪しても胸を張って案内できるレベルの工場へと進化しました。
また、組織をリードする人材の選定にあたっては、「部下への接し方が適切であること」「過ちがあれば謝ることができること」「事実を素直に受け止められること」といった基準を設けています。
キッチャヤー氏、ウィライラット氏、キッサダー氏の3人は、これらの条件を満たすだけでなく、実力も備わっており、他の社員からの信頼も厚いため、抜擢に対する社内の反発は一切ありませんでした。
会社を変えていく上で最も重要なのは、「人材育成」です。教育とそれを実行するためのトレーニングを通じて安定した業務を推進すると共に、作業の無駄を徹底的に削減し、社員がより多くの時間を新しい挑戦に充てられるようにすることこそが、経営者として果たすべき最大の役割だと考えています。
私たち日新電機タイの目指す会社像は、「いち早く変化に気づき、自ら変化を引き起こす、機動力のある会社」です。