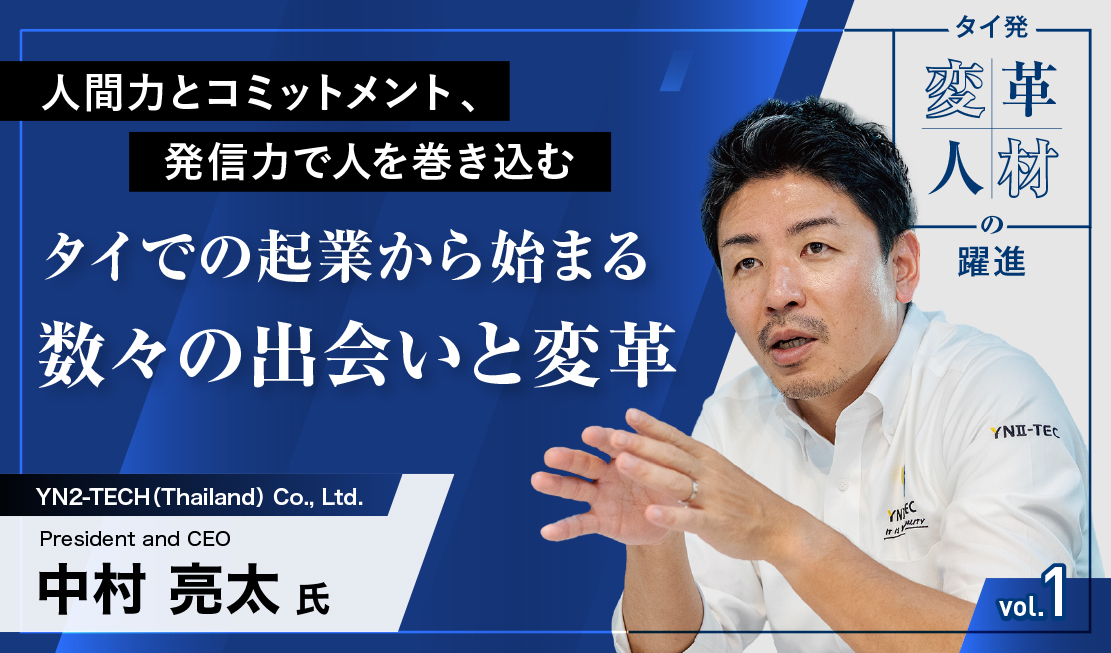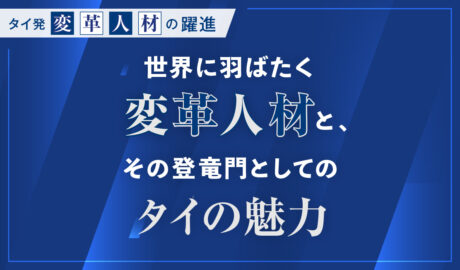人間力とコミットメント、発信力で人を巻き込む タイでの起業から始まる数々の出会いと変革
公開日 2025.04.10 Sponsored
本インタビュー連載では、変革人材、およびそうした人材を輝かせる舞台としてのタイの特徴の解像度を高めるべく、変革人材への取材内容を紹介する。第一回は、YN2-TECH (Thailand)Co., Ltd.(以下、「YN2-TECH」)代表取締役社長の中村亮太氏。起業家として次々と質の高い出会いを引き寄せる中村氏の物語は、タイで変革を起こす上での様々な重要な示唆があった。
聞き手: 一般財団法人海外産業人材育成協会(AOTS) バンコク事務所長 藤岡 亮介
新たに挑戦するものづくりを全方位で支援するYN2-TECH YN2-TECHの事業概要と、中村さんのこれまでの軌跡について YN2-TECHは設計や調達、販路拡大などを通じ、製造業のお客様をサポートするエンジニアリング商社ですが、グループ会社としては、生産・加工やデジタル化支援事業なども手掛けることで、「新たに挑戦する、ものづくり企業の全方位支援」を行うことを目指しています。
私は大学卒業後、メーカー、専門商社を経て父親が静岡で経営する機械商社の中村機工に3代目として入社しました。しかしほどなくして、父親への反発心もあり自ら新事業の開拓を模索する中、タイの広大な工業団地で生き生きと働く日本人に感化され、中村機工の関連会社としてYN2-TECHを起業。
ほぼ新卒のタイ人4人と事業を始めた当時は「日本のやり方を持ち込めば熱意で何とかなる」という楽観的な見通しを持っていましたが、多数の競合や、お客様の優秀なタイ人社員と若すぎる当社タイ人社員の間に立ちはだかる壁、日系企業にありがちな高コスト構造など課題は山積みで、すぐに考えが甘かったと痛感することになりました。
しかし、そうした課題を少しずつ乗り越え、自動車や空調機器などの分野で少しずつお客様を開拓した結果、今では45名の従業員を抱え、関係会社を含めると100名を超える組織になっています。また、新たに法人を立ち上げたインドなど、合計9カ国に向けての輸出やサービス展開をしています。
人の見極め力が強いタイは、実力試しに最適 変革の舞台としてのタイの特徴をどのように捉えているか タイは昔から多くの文化・価値観が交わる国であることから、タイの人たちは「人を見る目」が肥えていて、自分自身が本気でその人やビジネスに向き合っているかどうか、簡単に見抜かれてしまいます。そのため苦労も絶えない一方で、タイの人たちに認めてもらえた時の喜びはひとしおで、より大きな自信となります。そうした自信がタイからさらに他国に展開する際の支えになりましたし、世界で活躍したいと考える覚悟がある人がまずその実力を試す場所としては、タイは最適な国だと思います。
また、タイには会社規模に関係なく、意識の高いタイ人経営者も多くおり、彼らから学べることもたくさんあります。私にとっては、Applicad Public Company Limited.のプラパート・タンアドゥンラット前会長がその一人です。創業間もない頃、当社が資金難で危機的状況に陥った時、何度も彼のもとに通い詰めた結果、無名の若造だった私を信用し、資金繰りを助けてくれたことは、私の人間形成に大きな影響を与えました。
タイ人と向き合う際に気を付けている点は コミュニケーションを特に大事にしています。具体的には社員との会話で、会社の方向性や各人の役割を明確かつシンプルに例え話などを交えて伝えることを意識するだけでなく、相手が納得するまで粘り強く会話をしています。また、一番エネルギーを費やしているのが毎朝の15分間の朝礼で、会社方針や自分の想い、会社に対するコミットメントを、私も私以外も全力で社員に伝えることで、全員が同じビジョンを共有してブレずに進んでいけるチーム作りを行っています。
加えて、社員には断続的に新しく挑戦できる場を提供しており、こうした取組が、タイの人たちの好奇心・探求心を満たせる学びの場として機能しつつ、柔軟に変革に対応できる組織を作ることにも貢献していると考えています。
このように「変化」と「仕組み化」をうまく組み合わせた結果、当社の離職率は2%弱と極めて低く、同じ社員が継続してお客様のサポートをさせていただくことで、より信頼してもらえ、他社との差別化要素にもなっていると考えています。
今改めて問われる、 農業分野での変革 今まさに挑戦中の変革について教えてください タイ12年目の現在は、「タイのこれからの産業に役立ちたい」という目標を掲げ、これまで培ったノウハウも生かしながら、新たに農業・食品関連産業の高度化に挑戦しています。
具体的には、タイの肥沃な大地から採れる農作物の付加価値を最大化すると同時に、バリューチェーン全体でのCO2排出量や廃棄物などの環境負荷を最小化するべく、食品加工工程(搾汁・濃縮・乾燥等)の効率化・省エネ化に加え、農業残渣の飼料化・原料化を通じた有効利用の推進を、先進的な製品・技術を持つ、同郷静岡県出身の食品加工機械メーカーや、日系スタートアップとタッグを組んで行っています(図表1)。
出所:本人提供資料に基づきTHAIBIZ編集部が作成
既に搾汁など一部工程については、関連機器をタイビバレッジに納入するなど、徐々に成果が出始めていますが、タイの農業の持つポテンシャルを生かし切れるように、全方位で支援できるような陣容を整えていきたいと考えています。
また、農業分野の収益性や生産性向上は、どこの新興国でも改めて問われる課題となっているため、タイ以外での展開も中長期的には見越し、今後は経済産業省の補助金※1 も活用させていただきながら、パイナップルやココナッツといった汎用的な果物のバリューチェーンの高度化を、タイでの実証を通してまず実現し、タイにて関連製品の製造、およびO&Mの基盤を整えた後、他 ASEAN 諸国などで展開していきたいと考えています。※1 グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金
変革を起こすうえでの障壁や困難、乗り越えるポイントは これまでの挑戦と最も違う点は、タイの人たちから見ると農業は、自動車や空調機器などの「外から来た産業」ではなく、「地場産業」であるというところです。そのため、関係者と議論をしていても、本当にこの「よそ者」が、自分達が抱える社会課題を解決してくれるのか、とより厳しい目で人間力やコミットメントを見られている感覚があります。
そのため、まだまだ未熟者だなと痛感する一方で、人間力だけでなく、高い意識で取り組める組織力を、今後も継続して磨き、より良い人、良い会社になっていくことを社員全員で取り組みます。
また、社内的には 今回のチャレンジは拙速な 「収益化」を目指す事業とは位置付けておらず、むしろ短期的には人材育成戦略の一環として捉えております。タイに限らずではありますが、人は企業を支える重要な財産であり、ローカル化が進むタイでは、優秀なタイ人がタイ人コミュニティの中で鮮度の高い情報を得ることがますます重要になっています。
自分が趣味であるサッカーを通じて知り合うタイ人経営者たちも、モチベーションが高く優秀なスタッフを集めることにかなりの投資をしています。こうした中で、日本企業、特に日系中小企業が単発の採用イベントや標準的な社内教育プランを策定・実施するだけでは魅力的な人材を確保することはどんどん難しくなっていると感じます。
このような状況下で私は、真にタイの社会に根差した課題に果敢に挑戦し、その取組を関連する展示会や大学との産学連携イベントなどで積極的に発信することで、当社の若手人材や、大学生やその先生方、これまでの本業ではお付き合いの無かった企業の方々との触れ合う機会が増えました。
こうした新たな出会いを起点に、さらに積極的にコミュニケーションを取ることで、社内外に仲間を増やしつつ、今いるタイ人社員に「挑戦しがいのある現場」を経営者として提供することで彼らの当事者意識や、成長意欲も高めていきたいと考えています。
その結果、鮮度の高い情報を取って来ることができ、それを生かせる優秀なタイ人を確保・育成することを通じ、チーム全体の底上げを図っていけると私は信じていますし、こうしたチーム力の強化は既存事業にも大きなメリットがあると考えています。
発信力を通じた壁の突破 中小企業から変革を生み出すために必要なことは 確かに中小企業は様々な制約を抱えており、なかなか変革に踏み出せない企業も多くあると思います。しかしながら、自社で何でもやろうとせず仲間を募ることでそうした壁は克服できると私は考えており、そのためには自らのメッセージを対外的にも発信し、良質な出会いを自ら呼び込むことを心がけています。
タイでは、日本ではしがらみがあって絶対に実現しないようなチームを形成できることに加え、企業同士も日本国内の勢力図や規模にとらわれない連携を追求することができるのも面白い点です。そうした仲間にコミットメントを示すための資本提携や、タイ社員同士の具体的業務連携を組み合わせながら、今後も有機的なつながりを通じて、一緒に面白いことに挑戦する仲間を探し続けていきたいと思います。