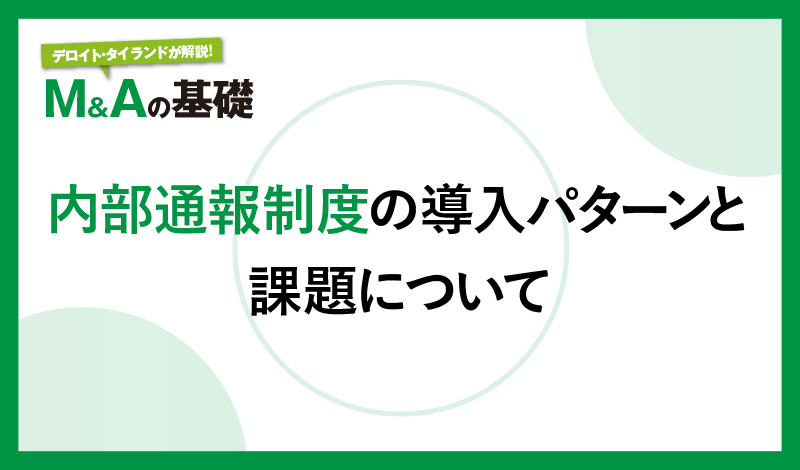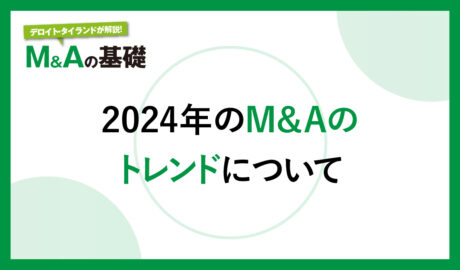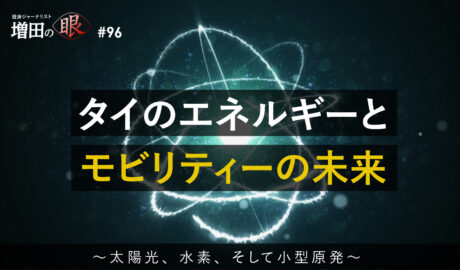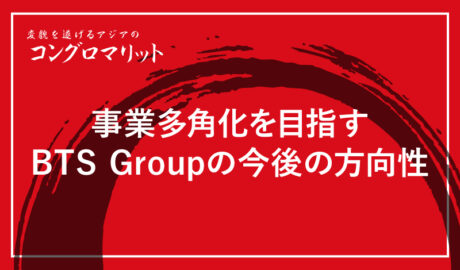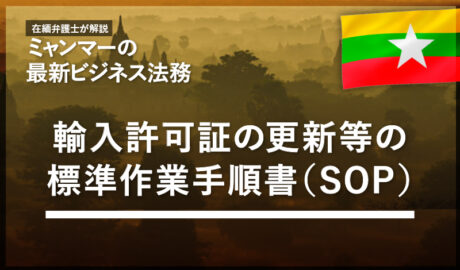内部通報制度の導入パターンと課題について
公開日 2024.11.11
事業成長のベースとなるガバナンス体制の強化にはさまざまな方法があり、内部通報制度はそのうちの一つの手段となる。タイでは必ずしも義務化されているわけではないが、最近は関心を持つ日系企業が増えていると感じており、今回はその導入パターンや課題について紹介する。
不正行為発見を目的とすることが多い内部通報制度
内部通報制度は不正行為の発見を目的に導入されることが多い。実際に、約40%程度※1が内部通報制度を通じて発覚すると言われており、内部監査や会計監査といった発覚経路よりも割合は高い。最近では公官庁関連の事案で内部通報制度が話題になったこともあり、ご相談をいただく機会が増えてきていると感じている。
※1 公認不正検査士協会(ACFE)
内部通報制度の導入についてはパターンが存在する。そのパターンを紹介しつつ、弊社がお客さまと接する中でよく伺う、内部通報制度でありがちな課題について触れていきたい。
内部通報制度の導入パターン
まずは、一般的な内部通報制度の導入パターンをご紹介したい。
①自社のみで内部通報制度を導入
外部のベンダーを使わず、自社のみで運用する。よく見られるのが、目安箱のようなものを食堂等に設け、人事部やコンプライアンス担当部署などが寄せられる意見を管理しているケースである。
②外部ベンダーのサポートを受け内部通報制度を導入: 弁護士事務所系
弁護士事務所が内部通報制度の運用サポートを行っているケースがあり、主に電話やメールで専門家が相談を受け付ける。グローバルで展開する弁護士事務所は各ローカル言語で相談を受け付けているようなケースもある。通報受付後に専門的なサポートが受けられる点がメリットとして挙げられる。
③外部ベンダーのサポートを受け内部通報制度を導入:ソフトウェア会社系
ソフトウェア会社が内部通報を受け付けるプラットフォームを提供し、社員が通報する。一般的にマルチチャネル(電話、メール、ウェブサイトのフォーム等)で提供されており、プラットフォームもITスタンダードに即した一定水準のセキュリティを兼ね備えたものが多い。コストは低くなる傾向にある。
④外部ベンダーのサポートを受け内部通報制度を導入:会計事務所系
デロイトを含めた会計事務所のグループ会社が内部通報制度の導入を支援するケースもある。そういった会社では不正調査なども行っており、そのノウハウを生かして通報受付後のアドバイスを行う。また、グローバルに展開している会社であればローカル言語サポートを行っているケースもあり、ソフトウェア会社のようなプラットフォームを独自開発して提供している場合もある。
弊社のサーベイによると、回答者の48%は何らかの形で外部のサービスベンダーから支援を得ていると回答している。一方で42%は内部通報制度を完全に社内で運用していると回答した※2。
※2 デロイト 2023 アジアパシフィック 内部通報調査レポート
内部通報制度でよくある課題
一般的には以上のような導入パターンが存在するが、特に自社で内部通報制度を導入した場合にありがちな課題をこちらで挙げていきたい。また、考えうる解決策についても簡単に記載した。
課題1:通報が寄せられても対処法が分からない
よくある声:通報が寄せられても、経験がないのでその後の対処法がよくわからない。自社のみでやっているか、もしくはシステム会社に運営を委託しているので、自社で解決しないといけないが、相談先もなく人も足りないので放置気味になってしまう。
解決策:専門家への相談も対象に含むサービスを利用する。場合によっては不正の芽となりうる通報内容(購買担当者が調達先と裏で繋がっている可能性があるなど)も寄せられるので、そういった場合は取扱いに特に注意を要する。信頼できる相談先を確保しておくのが重要である。
課題2:寄せられる案件の管理が煩雑である
よくある声:目安箱を設けており紙で報告を受け付けているので、紙の管理が煩雑。また、担当部署で処理しきれないような報告が寄せられ、他部署に協力を仰ぐ必要があるがうまく連携ができない。結局、目安箱に意見を上げても対応してくれるのかどうかが良く分からないので、誰も意見を寄せなくなる。
解決策:寄せられる件数が多いのであれば、システム管理が可能な外部ベンダーを利用するのも手である。また、内部通報のポリシーを見直し、通報のプロセスを明確化したり、案件の種類ごとに責任者を明確化させるという取り組みも考えられる。
課題3:内部通報の件数が実態を表しているのか不安
よくある声:最初に研修をしたので、制度の導入初年度は良かったが、その後年を追うごとに報告件数が減っていった。自社でコンプライアンス意識が高まって減っている可能性もあるが、本来的に報告してもらうべきものが上がってきていないのではないかという懸念がある。
解決策:朝礼やイントラネット等での定期的な周知、特に経営陣がしっかりと見ているということをメッセージとして伝えることが重要である。ネームカードやハンドブックに通報先を記載(通報先のウェブサイトのリンクに繋がるバーコードを掲載するなど)するケースもある。
まとめ
以上、実際に弊社に寄せられる声などもご紹介しつつ、特に自社で内部通報制度を運営する上での課題や考えうる解決策などについて述べてきた。自社で導入するのも安価ではあるかもしれないが、管理が煩雑であったりその後の対応に不安を残したりするケースもあるので、外部ベンダーを利用するのも一つの手である。
(※注)本文中の意見や見解に関わる部分は見であることをご了承ください。