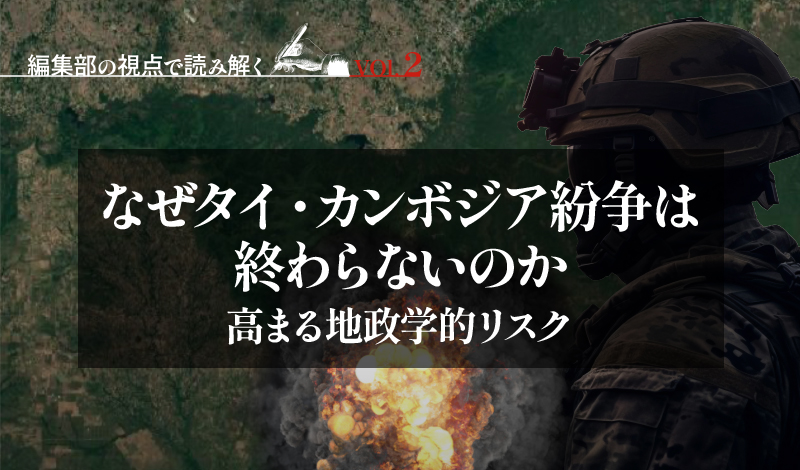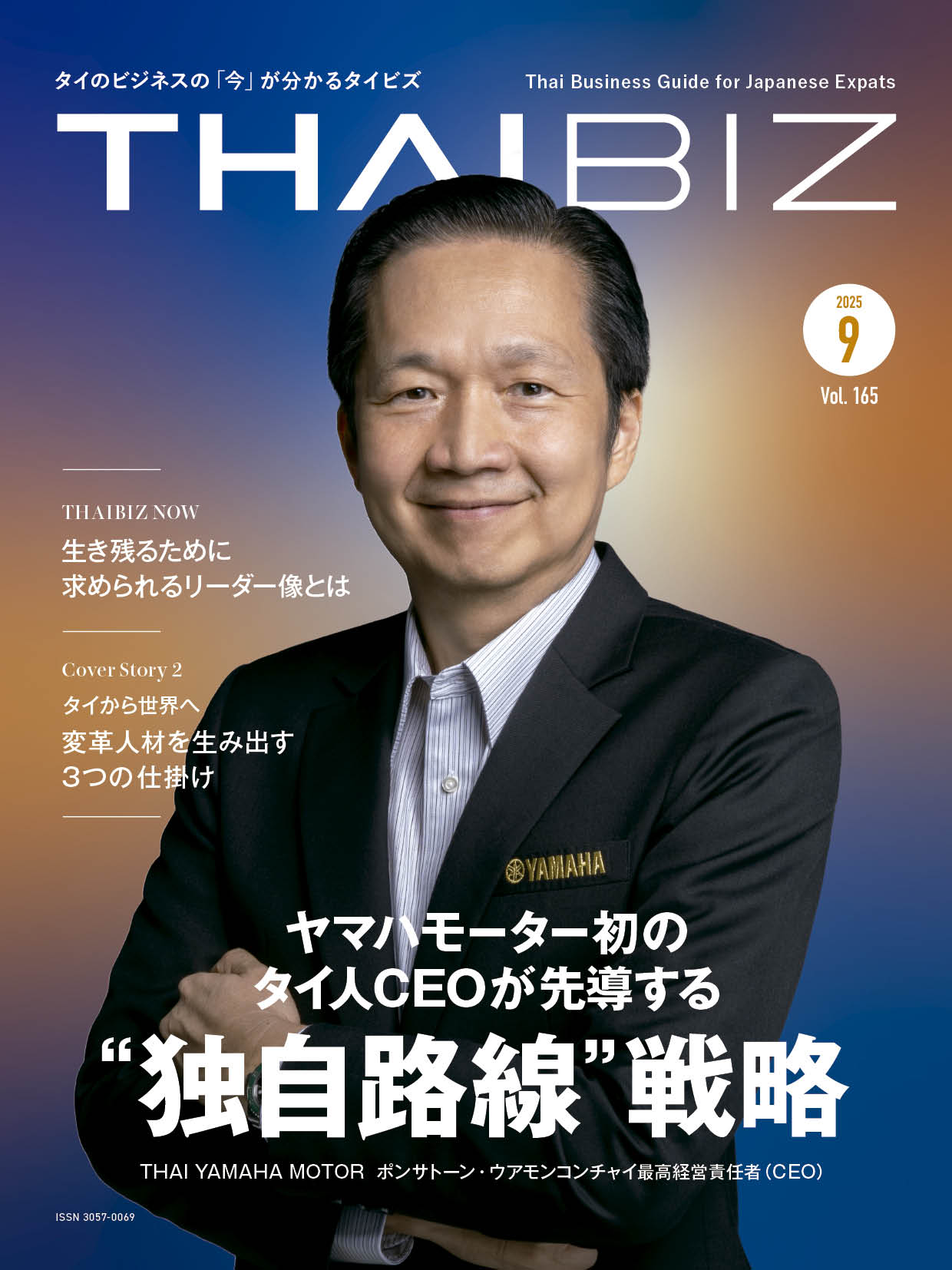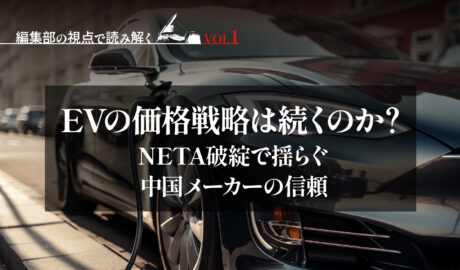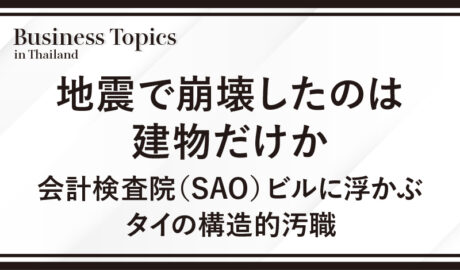THAIBIZ No.165 2025年9月発行ヤマハモーター初のタイ人CEOが先導する“独自路線”戦略
この記事の掲載号をPDFでダウンロード
最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中
なぜタイ・カンボジア紛争は終わらないのか – 高まる地政学的リスク
公開日 2025.09.10
タイとカンボジアの国境で、再び軍事衝突が発生した。背景には歴史的な領土問題に加え、国内政治や国際情勢などさまざまな要因がある。本稿では、対立激化の背景を整理しつつ、両国の緊張が貿易・物流・労働力を通じて日本企業に及ぼすリスクを探る。
再燃した5月28日の銃撃戦
5月28日、タイ東北部ウボンラチャターニー県のチョンボック地区で、タイとカンボジアの軍が交戦した。
カンボジア側が国境付近に建造物を設置しようとしたことを受け、タイ側が部隊を派遣。現地で10分程度の交戦となり、カンボジア兵1名が死亡、その後、現場周辺を巡回中のタイ兵1名が爆発物により負傷。このため、国境検問所が一時封鎖される事態となった。
両国の国境をめぐる対立は今回が初めてではない。2011年には世界遺産プレアビヒア寺院をめぐって複数回の衝突が起き、多数の死傷者が出た。
今回の衝突も同寺院にほど近い地域で発生しており、過去と同様の緊張状態が再び浮上した形だ。国境付近では違法な建築活動や密輸、カジノ経済の利権など複合的な火種が散在しており、今後も衝突を繰り返す可能性は否定できない。
偶発ではなく、構造的な対立
タイとカンボジアの国境をめぐる混乱の起点は、20世紀初頭のフランス植民地時代にさかのぼる。1904年、当時のサイアム(シャム)王国(現・タイ)はフランスと条約を締結し、「分水嶺(山の尾根など水の流れが分かれる自然地形)」を国境線とすることで合意していた。
地形に従えば、プレアビヒア寺院はタイ領に位置するはずだった。ところが、その後1907年にサイアムは、シェムリアップ、バッタンバン、シソポン(いずれも現在のカンボジア領)をフランスに割譲し、その見返りとしてトラート県やメコン川左岸の領土を取り戻す交換協定を締結。
この協定の直後、フランスが一方的に作成した新たな地図では、プレアビヒア寺院をカンボジア領として描いていた。地図は分水嶺を無視し、恣意(しい)的な境界線が引かれていた。
当時のサイアム政府は、独立維持を最優先に据え、フランスとの対立を避けるためにこの地図に抗議しなかった。この「黙認」が、のちに大きな代償を生むことになる。1962年、国際司法裁判所(ICJ)はプレアビヒア寺院の領有権をめぐる裁判でカンボジア側の主張を支持。タイが過去に異議を唱えなかったことが「黙示的な承認」と見なされたのだ。
根本は植民地時代に生まれた地図上の境界線のズレ
さらに地図の縮尺の違いも、混乱に拍車をかけている。カンボジアが主張の根拠とする地図はフランス植民地時代に1:200,000の縮尺で作成されたもので、地形の詳細が乏しい。
一方でタイは、1:50,000の詳細地図をもとに国境を主張している。このような「地図のズレ」は、現地の実効支配と国際法上の境界線の不一致を生み出し、今なお対立の火種として残り続けている。
筆者としては、ICJは平和的な手段による紛争解決の枠組みである一方で、「文書証拠」や「国際条約」といった形式的な論拠を重視しすぎる傾向があり、そこには国際政治の力学が作用している可能性も否定できないと考える。
ICJの裁判官15名は、国連総会および安全保障理事会によって選出されており、米国・ロシア・中国・英国・フランスといった安保理常任理事国が判決に一定の影響力を持つ。そのため、ICJの判断が、ときに「法の名を借りた正当化」として利用される可能性も否めない。
政権の正当化とナショナリズム対立を繰り返す背景
今回の対立には、単なる領土問題を超えた内政上の思惑が色濃く反映されている。カンボジアでは現在、フン・セン前首相から息子のフン・マネット首相への権力移行が進行中だが、この「世襲」体制に対する国内の反発や不満も浮上し始めている。
そうした中、政権の求心力を保つために“共通の敵”を作り出す必要があったとの見方が、タイの研究者から相次いでいる。今年8月にチェンマイ大学政治行政学部などが主催した合同シンポジウム1では、カンボジア指導部が「外部との対立を国内統合の手段として利用している」との分析が示された。
この見方は、教育現場でのナショナリズムの形成にも表れている。タマサート大学の論文2によると、カンボジアの中等教育の歴史教科書では、「タイは敵である」と理解させるような内容が見られ、過去の戦争や搾取の歴史が強調されているという。こうした教育は、国民感情の土台となり、対立構造を生みやすい社会的背景を作り出している。
一方、タイ国内の動きも無関係ではない。プレアビヒア寺院以外にも、チョンボック地区などではタイが長年管理してきた遺跡がカンボジアの主張対象となっており、両国で“地図上の正当性”を巡るせめぎ合いが続く。
今回の争いは、かつてプレアビヒア寺院をめぐって衝突が起きた10年以上前の対立と構造が似ており、同様の緊張が再燃したとの指摘もある。つまりこの国境紛争は、ただの地理的な境界線をめぐる問題ではない。政治的意図、教育、ナショナリズムといった複合的な要素が交錯することで、偶発的ではない「構造的な対立」として繰り返されている。
タイ経済へおよぼす影響
今回の衝突は、タイでのビジネスが周辺国を含む地政学リスクと不可分であることを改めて示した。物流や人材の動線は、国境の緊張ひとつで簡単に揺らぐ。
2023年のタイ・カンボジア間の国境貿易額は約40億バーツ(約170億円)にのぼると報告されており3、実際、交戦地となった国境地帯の複数の県は両国間貿易の重要拠点である。現在、すでに多くの企業がラオス経由や空輸への切り替えを進めているが、こうした対応はあくまで一時的な措置にすぎない。
一方で、今回の対立の背景には、単なる領土問題では説明しきれない“もう一段深い層”がある。現地では違法建築や密輸、カジノ経済、さらにはオンライン詐欺をめぐる利権が絡み合い、複数の火種がくすぶっている。
さらに、タイ貢献党(プアタイ党)が掲げる複合娯楽施設(エンターテインメント・コンプレックス)構想が、カンボジア側の既得権益と衝突しているとの見方もある。特に、フン・セン前首相一族とタクシン元首相との政財関係を背景に、こうした摩擦が表面化しやすい構造があったとも言える。
加えて、米国が停戦交渉への関与を引き続き模索しているとの報道もあり、カンボジア側にとっては、中国依存を見直す動きとも連動している可能性がある。
「タイプラスワン」の構想を支えるはずの国境地帯で、火種はくすぶり続けている。経済合理性の裏にある地政学的リスクに、あらためて目を向けるべき時が来ている。
>> 本連載「THAIBIZ編集部の視点で読み解く」の記事一覧
引用元