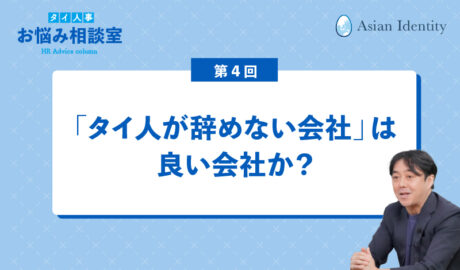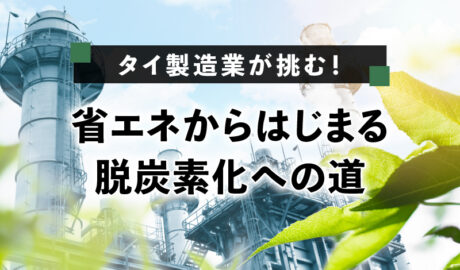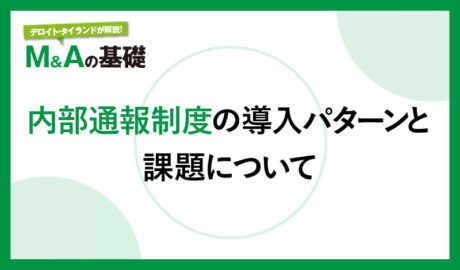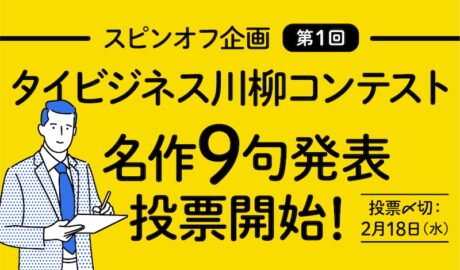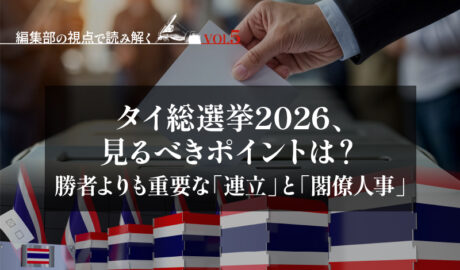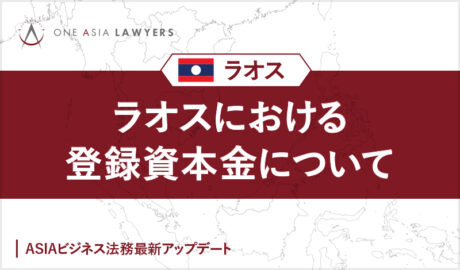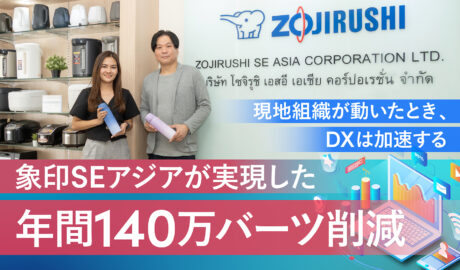最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中
民間企業との連携も強化し、持続可能な難民支援を ~UNHCRアジア・太平洋地域副局長の入山氏インタビュー~
公開日 2025.05.21
タイおよび周辺国には、紛争などから逃れた難民や国内避難民、無国籍者に加え、自然災害の被災者など、庇護を必要とする人の数は多い。そこに国際的な立場から支援を行っている機関の一つが、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)だ。
世界130カ国以上に事務所を置くUNHCRは、タイに二つの拠点を持つ。一つはタイおよび周辺国を管轄するタイ事務所、もう一つはアジア・太平洋地域の44カ国を管轄し、約1,600万人の難民、国内避難民や無国籍者の保護をサポートするアジア・太平洋地域局だ。
UNHCRは主に各国政府や非政府組織(NGO)などとパートナーシップを結び活動しているが、持続可能な支援には「民間セクターとの連携も必要不可欠だ」という。UNHCRのタイおよび周辺国での活動内容や、在タイ日系企業を含む民間企業との連携可能性などについて、UNHCRアジア・太平洋地域副局長の入山由紀子氏にインタビューした。
(インタビューは2025年4月30日、聞き手:THAIBIZ編集部)
 UNHCRアジア・太平洋地域副局長の入山由紀子氏
UNHCRアジア・太平洋地域副局長の入山由紀子氏
難民や無国籍者を庇護するために活動するUNHCR
Q. UNHCRの活動概要およびタイ・周辺国での活動内容について
入山氏:UNHCRは難民、庇護希望者、国内避難民(紛争などの理由で家を追われ国内で避難している人々)、帰還民、無国籍者を対象に、主に3つの活動を柱に支援を行っています。
一つ目は、国際保護。紛争や迫害により故郷を追われた人々の権利を守るために、基本的人権の庇護を促進します。二つ目は、緊急支援。紛争や自然災害などの緊急時にはいち早く、備蓄倉庫から物資を運び、シェルター、食料、水、医療など命を守る支援を提供します。常に迅速な支援が可能となるよう、人員配置等の備えにも力を入れています。三つ目は、恒久的解決に向けた国際的な調整と先導です。自主帰還、定住先での社会統合、そして第三国定住といった解決策を、各国政府やパートナーと連携しながら促進および調整しています。
UNHCRがタイで活動をスタートしたのは1975年です。現在ミャンマーとの国境付近に位置する一時的なシェルターでは約8万人のミャンマー難民がタイ政府の庇護を受けています。
さらに、タイには9万人弱の難民がおり、山岳部を中心に50万人以上の無国籍者が存在しています。他方、2024年10月、タイ政府は約50万人の無国籍者に居住権を給付する制度の導入を決定しました。同制度が実施されれば、約50万人がタイ国籍というアイデンティティを取得することができ、世界的な好例となるでしょう。
Q. こうしたタイ政府の決断には、UNHCRの働きかけも影響しているのか
入山氏:どうすればすべての人に国籍を保障することができるのか、受入国の政策への提言を行うこともUNHCRの重要な役割の一つです。タイ政府へはUNHCRタイ事務所が継続的に無国籍者への解決策を探る働きかけを行っていたほか、UNHCR全体としても、2014年から無国籍ゼロを目指したキャンペーン「#IBelong Campaign」を実施してきました。その他、他国の好例などを学ぶワークショップを政府やパートナー向けに開催するなど、キャパシティビルディングのサポートも行っています。
ミャンマー地震の被災地にもいち早く緊急支援を実施
Q. 2025年3月28日に発生したミャンマー地震の被災地への支援状況について
入山氏:ミャンマーのマンダレーおよびネピドーにもUNHCRの拠点があり、スタッフも常駐しているため、地震発生直後から迅速に緊急支援活動を開始することができました。具体的には、地震で被災された方々に、ヤンゴンとドバイの備蓄倉庫からテントや寝床、水汲みバケツ、キッチンセットなどの援助物資を届けています。UNHCRは、他の国連機関や市民団体と協力しながら、被災地におけるシェルターと援助物資供給の調整役を担っています。
ミャンマーには、震災前から約350万人の国内避難民がおり、そのうち210万人が被災地域に居たと言われています。現在約2,000万人が人道援助を必要としている、「危機中の危機」と言われる状況です。UNHCRは、最大120万人への支援を可能とする1,590万米ドルの資金支援をいち早く世界のドナーに呼びかけ、各国の政府、企業、個人から支援金が集まりつつありますが、未だ十分ではありません。
大規模な震災が起きた際、震災直後はメディアなどで大きく取り上げられるため支援が集まりやすいのですが、日常的に様々な出来事が起こる中で、時の経過とともに注目度は低下していきます。ミャンマーの紛争や地震により支援を必要としている人が数多くいることを、われわれとしても引き続き発信していきたいと思っています。現在も呼びかけを継続していますので、THAIBIZ読者の方でご協力いただける方がいらっしゃいましたら、ぜひホームページをご覧ください。
 ミャンマー被災地へ物資を運ぶ様子(写真提供:UNHCR)
ミャンマー被災地へ物資を運ぶ様子(写真提供:UNHCR)
Q. タイや周辺国において、迅速な緊急支援を実現するために工夫していることは
入山氏:タイを含むアジア太平洋地域の緊急支援で欠かせない機能の一つが、日本政府の援助により25年前に立ち上がった「eセンター(人道援助活動のための訓練センター)」です。これは、同地域の政府やNGOの第一線で活動する人を対象としたトレーニングコースです。元は東京に拠点がありましたが、現在はタイにチームがあり、実地での安全訓練や平和に向けた人道的交渉法などを学ぶオンライン研修を行っています。UNHCR内部でも緊急援助のトレーニングは行っていますが、eセンターのコースを通じてパートナーとの連携を強化することで、迅速な緊急援助を実現しています。
ちなみに、2023年12月の「グローバル難民フォーラム(Global Refugee Forum :GRF)」で日本政府がeセンターのアフリカ版の支援を宣言(プレッジ)したことを受け、2024年からはアフリカでも同トレーニングプログラムが展開されています。
予測可能な事態への対策・準備も徹底しています。例えば、バングラデシュの難民キャンプ周辺では毎年モンスーンが発生したり、頻繁に火災が起きたりします。UNHCRとしても備えは施しますが、難民の方々の中から防災ボランティアを募り、彼らを訓練することで防災につなげています。UNHCRは、難民の意思と要望を反映する支援活動(Refugee Centered)を原則としているためです。
「社会全体で取り組むパートナーシップ」で持続可能な支援を
Q. タイでは、どのようなパートナーとともに活動しているか
入山氏:主にタイ政府、NGO、地域コミュニティの皆様と連携しています。民間セクターとの連携については、日本では財源支援を超えた“盟友”と呼べるような関係性を築いている企業や経団連との連携事例などもありますが、タイにおいては今後機会が広がっていく分野だと考えています。
タイで暮らす難民の多くは、人道援助に頼るのみならず、社会の一員として働き貢献したいと願っています。教育や医療へのアクセスなど課題が多い中で、日タイ基金の立ち上げなど、在タイ日系企業を含む民間セクターとの連携方法を模索しているところです。
他国では、日系企業による難民の雇用、UNHCRと企業が連携した政策提言、社員やお客様への難民問題の周知など、さまざまな連携事例があります。財政的な支援も大変心強いのですが、それを超えた「社会全体で取り組むパートナーシップ」が持続可能な支援を実現し、ひいてはタイ政府やタイの皆さんへの貢献の機会につながると考えています。
Q. 民間企業との連携が新しいビジネスにつながった事例は
入山氏:バングラデシュの難民キャンプでは、日本の民間企業による職業訓練で裁縫技術を習得した難民が制作した女性用衛生用品をキャンプ内の難民に配布するほか、同製品を商品化する可能性も模索しています。アフガニスタンでは、世界銀行(WB)および国際金融公社(IFC)との共催で、UNHCRが自立支援している国内避難民や帰還民の女性が製作するカーペットや蜂蜜などの製品を、現地企業に紹介する商談会イベントを開催しています。
このように、新しいビジネスモデルが生まれつつある中で、タイでも民間企業との連携においては多大な可能性があると信じています。

民間企業とも手を携え、より良い明日をつくっていく
Q. 在タイ日系企業へのメッセージは
入山氏:まずは、世界には今なお1億2,000万人を超える庇護を求める人々が存在していることを知っていただくとともに、タイ周辺の地域に関しては、ミャンマー地震の被災地支援へのご協力と、今後の復興に向けた長期的なサポートをお願いしたいです。
UNHCRとしては、昨今人道援助のニーズが多様化する中で、民間企業の皆様からの斬新かつ創造的なアイデアに倣って活動していきたいと考えています。互いに力を合わせて、手を携える分野を見つけていくことによって、より良い明日につなげたいと思っています。
すでにUNHCRをサポートしてくださっている個人の方や企業の皆様には改めて感謝を申し上げるとともに、これまで連携機会のなかった方々とも協力機会を模索したいと考えていますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
>>本連載「日タイ経済共創ビジョン」の記事一覧