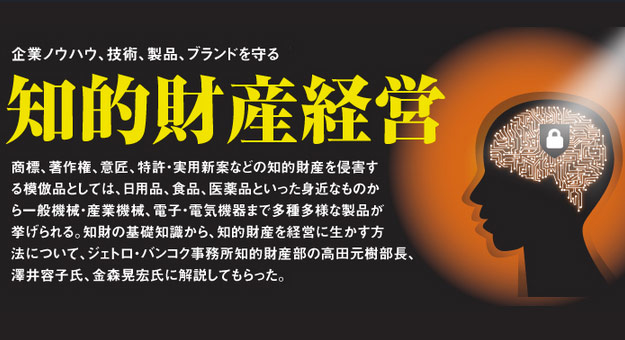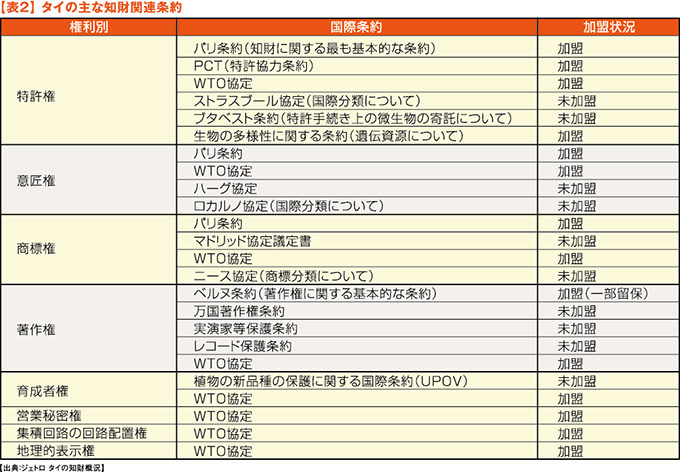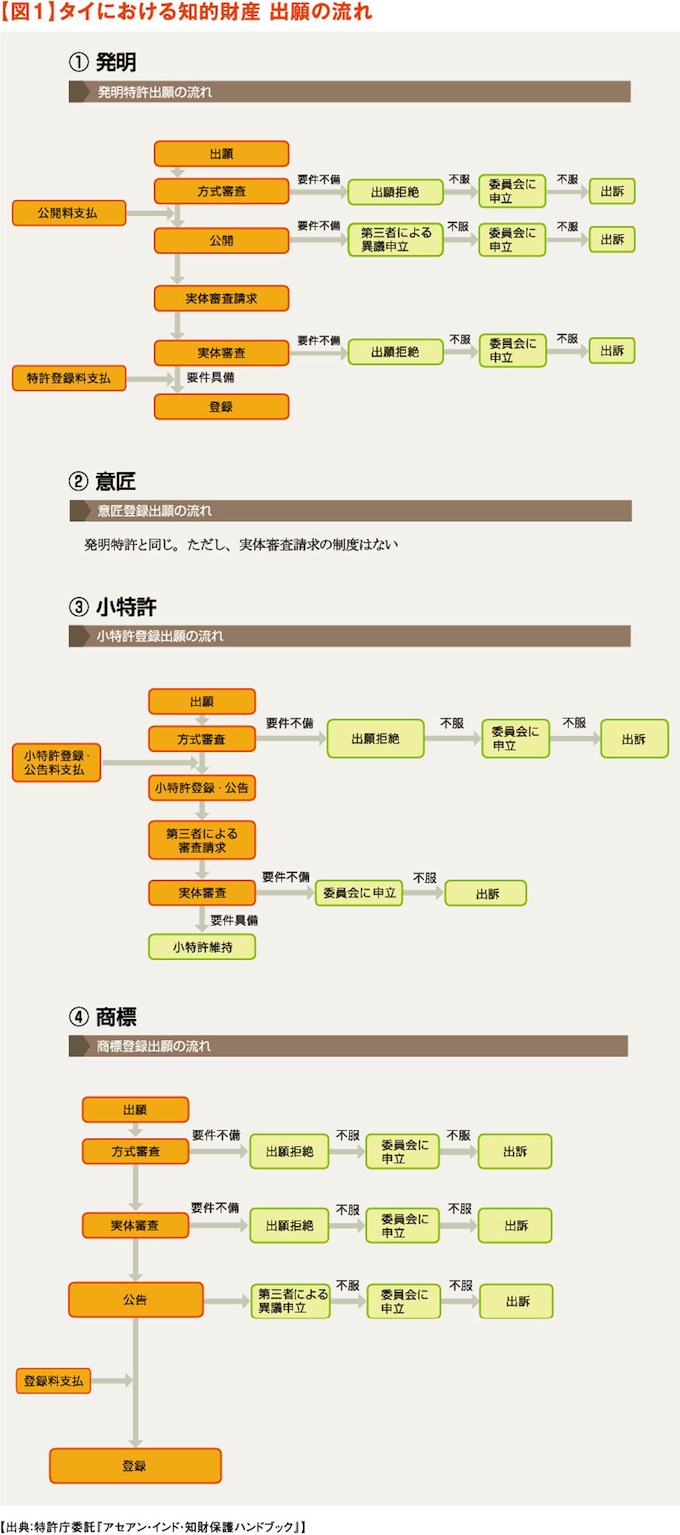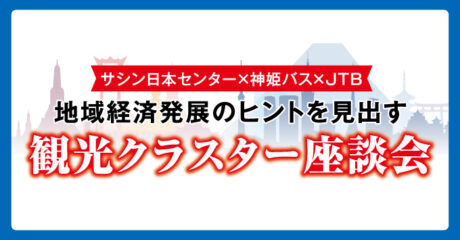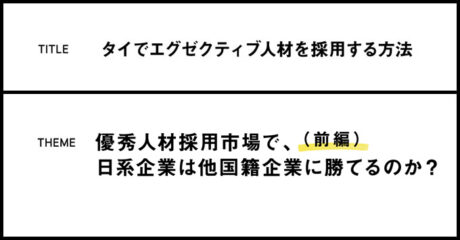Category カテゴリー
Regulars 連載
- 編集部の視点で読み解く
- Open Innovation Talkリポート
- 日タイ経済共創ビジョン
- 在タイ日系企業経営者インタビュー
- タイ企業経営者インタビュー
- 在タイ日本人駐在員の挑戦
- タイ発変革人材の躍進
- 日系スタートアップ
- THAIBIZ NOW
- 日系企業の強い味方!タイで頼れる支援機関 - JICA
- タイ・ASEANの自動車ビジネス新潮流 - 野村総合研究所
- タイ経済概況 - SBCS
- ASEAN経営戦略 - Roland Berger
- タイ人事お悩み相談室 - Asian Identity
- 外資規制 基礎から応用まで - 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
- アジアのコングロマリット - 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
- M&Aの基礎 - Deloitte Thailand
- MEKONG 5 JOURNAL - みずほ銀行バンコック支店メコン5課
- 経済ジャーナリスト・増田の眼
- タイビジネスインサイト - NNAアジア
- ベトナム・ビングループ主席経済顧問、川島博之が読み解くアジア
- 日系企業が切り拓くタイの社会課題解決 - JICA
- 中小企業経営論 - BizWings
- 知らなきゃ損する!タイビジネス法務 - GVA / TNY法律事務所
- ASIAビジネス法務 最新アップデート - ONE ASIA LAWYERS
- 聞きたくても聞けなかった、タイの税金事情 - J Glocal Accounting
- ベーカー・マッケンジーのリーガル・イノベーション
- ミャンマーの最新ビジネス法務 - TNY国際法律事務所
- リブ・コンサルティングの経営戦略
- 市ICHI製造業DX特集 - Manufacturing Expo 2024