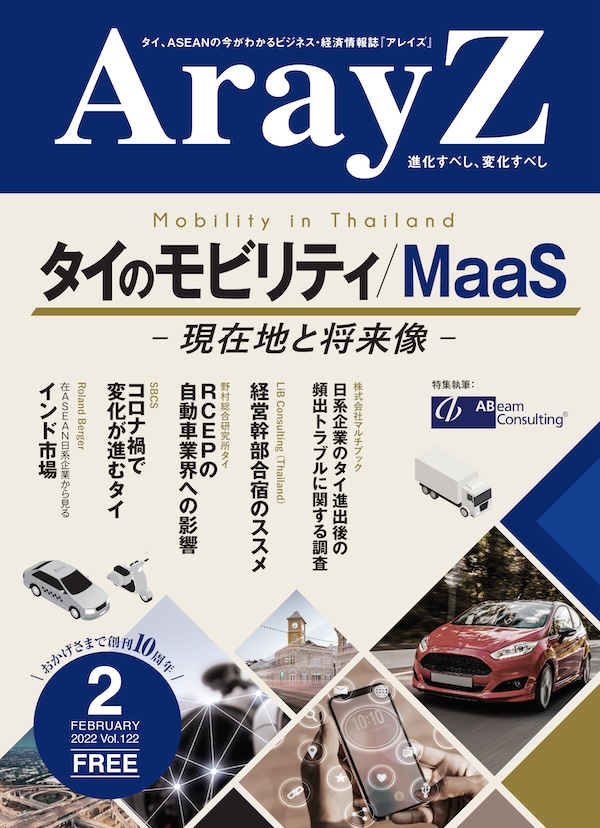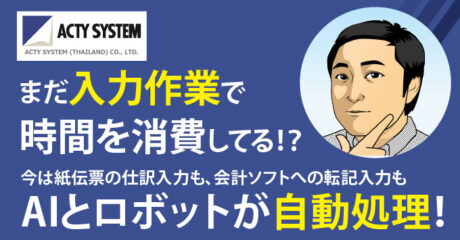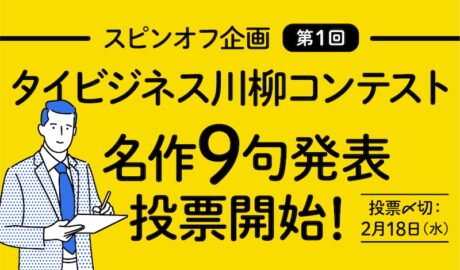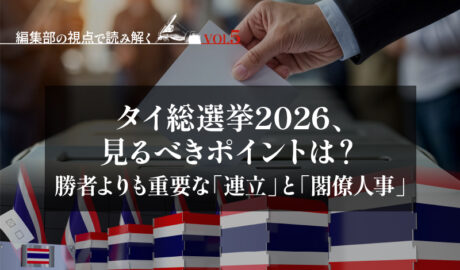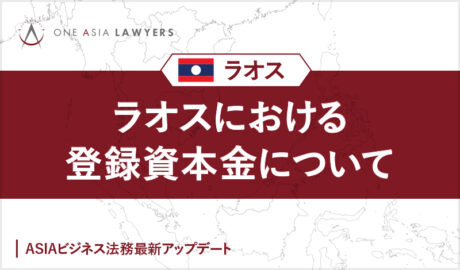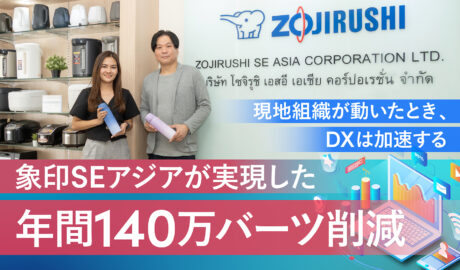タイのモビリティ/ MaaS – 現在地と将来像 –
公開日 2022.02.03
モビリティの考察 前頁のグルーピングを前提に、各グループのモビリティ環境と今後の将来像を考察する。
❶ 観光中心(プーケット・クラビなど) 1人当たりのGPPと世帯当たりの車両数の関係で言うとGPP、つまりは人々の購買力に関わらず車両数が多い地域と捉えることができる。
これは、観光客用に用意されている車両が多く、レンタカー等観光客向けのモビリティサービスが発達していると予想される。
例えば、グループ①に属し、世界的に有名なリゾート地であるプーケットでは、リムジンタクシーやタクシー、バス、トゥクトゥクやレンタカーが観光客用に多く存在する。
それでは、地域住民はどのようなモビリティライフを送っているのだろうか。また、どのようなモビリティが求められるのだろうか。19年に国際交通安全学会がプーケットで実施した調査結果(注1)が参考になる。
(注1)Khaimook, Sippakorn & Kento, Yoh & Inoi, Hiroto & Doi, Kenji. (2019).
調査では、モータリゼーションによる交通事故の増加を背景に、MaaSアプリで人々の行動を変容できるか実証実験が行われた。
調査用に作成されたアプリでは、目的地や出発~到着までのルートの検索、検索時の移動手段・所要時間・費用・安全性(事故数の統計や交通量から算出)・ウォーカビリティ(歩行し易さの指標を複数移動手段の接続性、駅周辺のスポットの立地、歩行時の快適さや安全性等から算出)の比較が可能であった。
また、公共交通機関としてはプーケットタウン・パトン間を結ぶバンやツアーバス、エアポートバス、プーケットスマートバス、ピンク/ブルーバス(現地のソンテウ)のデータが活用された。
このアプリを用いたユーザー調査の結果、調査チームは「交通安全に対する認知度を高めることはできたが、より公共交通機関の活用を促すような行動変容は起こせなかった」と結論づけている。
その理由として、地域住民にとってバイクや徒歩での移動の方が公共交通機関より利便性が高い、と認識されていることが挙げられており、慣習を変革させるには「地域のユーザーに向けたインセンティブの設計やデータの正確性を担保し、アプリに対する信頼を構築することが必要だ」と述べられている。
ここから考えられるのは、欧州のように公共交通を前提に複数移動モードを統合したモビリティサービス(以後、統合型サービス)は、一律に成功するものではないということである。そもそも公共交通の利便性が低い、あるいは、その利便性が認識されていない地では有効ではない。
観光客と地域住民でニーズに違い
グループ内の別の地域も見てみよう。チェンマイにおいては、庶民の足はソンテウである。公共交通の発達具合からも、地域住民はバイクやソンテウを移動手段に利用しており、鉄道からバス等複数の公共交通を乗り継いだ複雑な移動は行われていないと推測される。
これらを踏まえて、グループ①に求められるモビリティを考察する。先述の通り、レンタカー等観光向けの車両やモビリティサービスが提供されているが、地域住民に必要とされるモビリティとは異なる。
観光客向けには日本でも取り組みが進み、「観光MaaS」として認識されているモビリティサービスが有効な可能性がある。モビリティと観光コンテンツを統合し、観光地一帯で利便性と収益性を高める取り組みだ。
例えば、東急、JR東日本、伊豆急行が日本の伊豆地域で取り組む「Izuko」は、公共交通に加え、伊豆での観光体験もアプリ上で予約・決済が可能で、同時に地元事業者と連携したオリジナルの観光体験を創出する取り組みを行っている。
現地の交通事業者の巻き込みはハードルが高いだろうが、タイでも観光事業者中心にレンタカー等観光客向けのモビリティサービスやソンテウといった地域の足、地域の観光スポットと有機的に繋がったサービスを展開、観光客向けの車両の遊休時には地域へ貸し出す、といった世界観が実現すると、観光時の利便性向上、地域のモビリティサービス全般の品質向上、効率向上が期待できる。
❷ 工業中心+観光(アユタヤ・チョンブリーなど) 1人当たりのGPPと世帯当たりの車両数の関係で見ると、GPPの値が同等のグループ③と比較して車両が多い地域と捉えることができる。
これは、産業としては工業中心である一方、観光地も有するエリアのため、観光客向けの車両が多いとも推測できる。グループ②に属するチョンブリーでは、観光地のパタヤ市内において、ソンテウやタクシー、路線バスが交通手段として存在する。同グループのアユタヤも観光名所を擁する県である。
地域住民の目線で見ると、このグループは日系企業も多く進出する工業地帯を含む。企業が用意しているシャトルバスで従業員が通勤する姿が多く見られることも、このグループの特徴だ。実際に、チョンブリーには企業用シャトルバスを扱う会社が数多く存在する。
このような状況下、グループ②の地域目線のモビリティで有効なのは、製造業企業を主体とした車両の効率活用の仕組みだと考えられる。
このグループでも、都市鉄道やバスといった公共交通の発達レベルは高くないため、統合型サービスは機能しない可能性が高い。であれば、既存の車両の活用の幅を広げるという視点で、地域に存在する企業用シャトルバスに注目しようという考え方である。
観光地も有するため、グループ①のように観光向けのモビリティサービスに取り組むのも一手だが、その際にも一定の品質で提供される企業用シャトルバスを活用し、時期によって企業の保有する遊休車両を観光客向けに転用する等の工夫で、収益性の高いモビリティを目指すことができる。
❸ バンコク近郊+工業(ノンタブリー・サムットサコーンなど) グループ③は、1人当たりのGPPと世帯当たりの車両数の関係では、GPPの値が同等のグループ②と比較して車両数が少ない地域と捉えることができる。
これは、グループに属する県が主にバンコク近郊の運河が広がる都市であり、車以外の移動手段として水上交通が定着していることに理由があると推測できる。
グループに属する県を見ると、チャオプラヤー川流域であるノンタブリーや、タイ湾に面するサムットサコーンがある。これらの県は、タイ運輸省海事局の公開している19年のデータによると、高速艇の乗客数が多い都県トップ3(1位バンコク、2位サムットサコーン、3位ノンタブリー)に入っている。特にノンタブリーとバンコクはチャオプラヤーエクスプレスで結ばれており、人々の通勤の足として利用されている。
また、グループ②と同様に工業地帯の従業員が企業の用意したシャトルバスで通勤する姿も見られ、昨今はバンコク首都圏で次々と新線開業されているBTS、MRTといった都市鉄道が伸びてきているエリアでもある。
従来の水上交通との相乗効果で、比較的車を所有せずとも生活しやすい環境であると捉えられる。
これらを踏まえると、グループ③ではグループ②のような企業用シャトルの活用と組み合わせで、都市鉄道や水上交通と連携した新たなモビリティサービスが有効となる可能性が高い。
❹ 商業都市+農業(コーンケーン・ナコンラチャシマーなど) 1人当たりのGPPと世帯当たりの車両数の関係では、GPPの値が同等のグループ⑤と比較して車両が多い地域だ。
これは産業構造の話で触れた通り、双方とも農業比率が比較的高いグループではあるが、グループ④には商業都市が含まれる。より経済活動が活発であることから、商業用車両や通勤・買い物等における日常の足として車の必要性が高く、数値の差異が生まれていると推測できる。
グループに属するコーンケーンは南イサーンの経済の中心都市であり、学生都市でもある。バンコクを起点に全国へ延びるタイ国有鉄道(以後、国鉄)の駅は存在するものの、日常の足となるような都市鉄道は通っていない。タクシーも走行しているが、ソンテウが日常の足となっている。
また、東北地方最大の都市であるナコンラチャシマーも国鉄駅を有するが都市鉄道は通っていない。ソンテウ、路線バス、トゥクトゥク、人力車といった移動手段が存在している。
このグループでは、政府の支援による鉄道等都市部の公共交通インフラの整備を期待したい所だが、モビリティサービスとしてはライドヘイリングやカーシェアリングのネットワークを広く張り巡らせることで、商業都市と郊外・農業地域を繋ぐようなモビリティが求められる可能性が高い。 また、商業物流の共通化・効率化といったフリート向けのモビリティサービスの機運も高いグループであるとも想定される。
❺ 自然+農業(トラート・メーホンソーンなど) グループ⑤は、1人当たりのGPPと世帯当たりの車両数の関係で言うと、双方の数値が最も低いグループである。
このグループには、手つかずの自然が残る東部のトラートや、ミャンマーとの国境の山岳地帯に位置し、深い森に囲まれた北部のメーホンソーン等が属する。
さらに、東北部の田園地帯や南部のジャングル地帯も含まれるこの地域では、基本的な移動手段としてはソンテウが普及している。
このような地域では、市場原理が働くマーケットとしてモビリティサービスを展開させることは困難であるため、政府主体で地域開発を進めることが求められる。
❻ バンコク タイの政治・経済・教育・文化の中心地のバンコクは、先述の通り世帯当たりの車両保有数が群を抜いて高いだけでなく、移動手段も充実している。都市鉄道のBTSやMRTに加え、タクシーやトゥクトゥクも数多く走行している。
また、運河が発達しているため水上交通が庶民の足として根付いており、チャオプラヤー川で運行している「エクスプレス・ボート」は市内の重要な交通手段である。
一方、交通渋滞は非常に深刻だ。位置情報技術を開発するオランダのTomTomは、「トラフィック・インデックス」という指標を用いて、世界50以上の国の約400都市を対象とした渋滞ランキングを発表している。
バンコクは18年ワースト8位、19年11位、20年10位と一貫して上位である。しかし、バンコクは人口が多く、モビリティサービスを展開するマーケットとしては魅力的だ。後で紹介するが、複数のモビリティサービスプレイヤーが参入をしてきている。
移動基盤となる公共交通、モビリティサービスのプレイヤー、さらには渋滞という社会課題が存在するバンコクの環境を鑑みると、公共交通含むモビリティサービスの活用を促し、自家用車利用を抑制するような統合型のサービスの土壌が唯一整っており、その必要性も高い地域だと考えられる。
次の章では、バンコクに焦点を当て、この統合型サービス実現に向けて詳細に考察をしていく。
【小括】立ち返るべき視点、地域の多様性 ここまで、モビリティは人の生活に密着するものであり、サービスの設計に向けては地域の多様性が重要であることを理解するため、タイの各都県をグループ分けし、モビリティの現状や将来の可能性を考察してきた。
実際には、各地域の多様性はここまで提示してきたいくつかの指標以上に複雑な要因によって構成されている。そのため、グループとしての捉え方でなく、それぞれの地域と向き合いながら、また、生活者の方々を主役にしながら、方向性を見出していくほかない。
しかし、このような簡易分析からも生活やモビリティを取り巻く環境、求められる将来像、巻き込んでいくべきステークホルダーの多様性が見えてくるだろう。
モビリティ関連の事業者には、本稿の示唆を議論の端緒に活用いただき、それぞれの地域で議論がなされることで、生活者に寄り添った持続可能なサービス創出に繋がれば幸いだ。