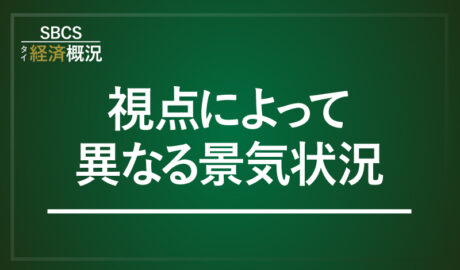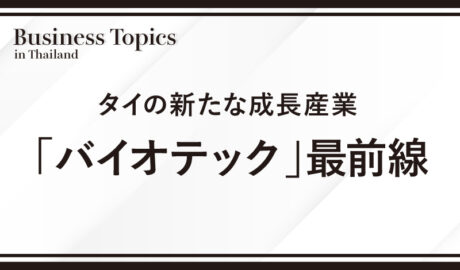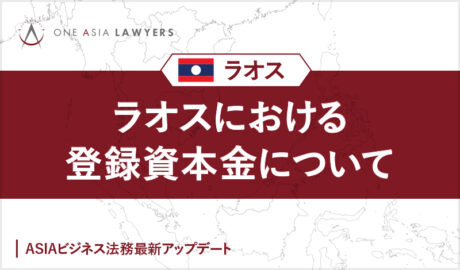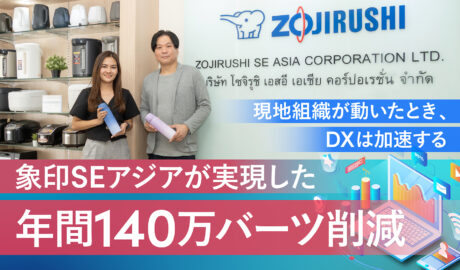タイ自動車産業の新時代は研究開発とソフトウェア人材が鍵 〜チュラーロンコーン大学工学部のパイロード教授とナックシット助教授〜
公開日 2025.08.28
電動自動車(EV)の普及や中国メーカーの台頭といった変化の波が押し寄せる中、タイの自動車産業は今、大きな転換期を迎えている。長年生産拠点としての地位を築いてきたタイにとって、こうした変化は企業だけでない。技術人材を育てる教育現場でも、時代に即したアップデートが求められている。
そこで今回は、チュラーロンコーン大学工学部機械工学科のパイロード・シンハタナッドキッド教授とナックシット・ヌムウォン助教授に、産業界の動向、機械工学分野における若者の関心、そして大学と民間企業の連携の可能性について話を伺った。
(インタビューは4月28日、聞き手:mediatorガンタトーンCEOとTHAIBIZ編集部)
チュラーロンコーン大学工学部機械工学科のナックシット助教授(左)、パイロード教授(右) 機械工学はすべての知識の「背骨」 Q. チュラーロンコーン大学と工学部について パイロード教授: チュラーロンコーン大学は、約4万3,000人の学生を抱え、22の学部(Faculty)および学部に相当する部局(School)があります。工学部は創立111年の歴史を誇り、約6,000人の学士から博士課程までの学生、300人の講師、300人の職員が所属しています。現在、12の学科(14の専攻)と6つの国際プログラムを提供しています。
国際プログラムでは、①自動車設計・製造、②航空宇宙工学、③情報通信工学、④ロボティクス・人工知能工学、⑤ナノエンジニアリング、⑥化学プロセス工学、を提供しており、今年「半導体工学」プログラムの入学が開始される予定です。
機械工学科では、①学士過程:機械工学と自動車工学、②修士過程:機械工学とサイバー物理システム(CPS)、③博士過程:機械工学、の5つの専攻を提供。学士課程では年間約100人の学生を受け入れており、機械工学専攻が85人、自動車工学専攻が15人に分かれています。なお、同学科の博士過程までの学生総数は約400人となっています。
Q. 現在、学生における学科・専攻選択の傾向は パイロード教授: 工学部で最も人気のある学科は「コンピュータ工学」です。また、人工知能(AI)とソフトウェアがトレンドになっているため、最近は学生の「ロボティクス・人工知能工学」への関心が高まっています。しかし、機械工学はやはり重要で、同分野の知識はすべての学科をサポートする「背骨」のようなものだと考えています。
ナックシット助教授 :チュラーロンコーン大学の学生の多くはタイの大手企業で働くことや研究開発などの技術的な職業、テクニカルサポートの仕事に魅力を感じる学生も少なくありません。
パイロード教授: また、海外での就職を希望する学生も多くなっています。最近では、大学のジョブフェアに来た日本企業が人事担当者を通じて学生を採用した例もありました。一方、当校にエンジニアを派遣し、教員と話し合って採用活動をする外国企業もあります。これは日本企業にとっても興味深い手法ではないでしょうか。
また、学生は就職に対して自分なりの条件を持っており、希望の仕事がまだ見つからない場合はギャップイヤーを取るのが一般的です。
研究開発に重点を置き、新たな成長エンジンの発見が必要 Q. 大学は産業の変化にどのように適応しているか ナックシット助教授: タイの自動車産業は1960年代に始まり、1990年代にピークを迎えました。私はトムヤムクン危機(1997年のアジア通貨危機)の前に自動車学科を卒業し、トヨタ自動車に就職しました。当時はほとんどが生産と生産準備の仕事で、トムヤムクン危機の後は日本企業がタイを輸出向けの生産拠点とするためにタイに進出したため、さらに生産が伸びていきました。大学でのカリキュラムも産業の動向に合わせて、生産に関する内容が中心となりました。
しかし時が経つにつれ、生産に焦点を当てるだけではタイの付加価値を生み出すことにつながらないと考えられるようになりました。
そこで、より高度な知識や技術に対応できる人材を輩出しようと、カリキュラムは研究開発に重点を置くように調整され、数十年にわたって実施されてきました。タイの研究開発はまだ国際的に目立った存在にはなっていませんが、現在タイでは研究開発の仕事が増えており、地域レベルではかなり突出し、以前と比べると目に見える変化があります。
今後は産業の変化に対応できるよう、継続的なアップデートが不可欠でしょう。また、現在は環境や自動化など、あらゆる産業に共通する課題がたくさんあります。そのため、自動車工学科の卒業生のスキルは自動車だけにとどまらず、これらについても理解しなければなりません。
Q. タイ自動車産業の現状は ナックシット助教授: タイには、タイ企業や合弁企業、外資系企業など、さまざまな自動車関連企業がありますが、タイ企業の割合は少なく、委託生産が中心となっています。しかし現在、この委託生産は発注元のニーズに基づいたデザインの提供まで求められるなど、競争が激化しており、厳しい市場となっています。多くのタイ企業は研究開発に十分な投資をしていないため、引き続き委託生産を行わざるを得ないのも現実です。
また、EVの普及が進みつつあるものの、タイの部品メーカーはまだ従来の部品の製造にとどまっており、EV用の新しい部品はあまり製造を任されていません。EV支援策により中国系の自動車メーカーが続々とタイに進出し、業界全体には変化が起きていますが、国内の雇用や技術移転につながっているとは言えません。つまり、タイは現在EVサプライチェーンへの本格的な参入が難しい状況です。
当初、タイが中国系EVの生産拠点として、世界市場への輸出のハブとなると見込まれていましたが、米国の政策といった外部要因や国内市場の収縮が障害となり、厳しい状況に直面しています。加えて、競争相手であるインドネシアやマレーシアが市場でのシェアを伸ばす中、タイがどのようにして新たな成長エンジンを発見して適応していくかが、今後の課題となるでしょう。
トレンドを見越し、民間企業との連携をさらに強化 Q. 市場の需要に応える人材を生み出すために大学が取り組んでいることは ナックシット助教授: 市場の需要に合わない人材を輩出する問題は、まるで「鶏が先か、卵が先か」のような解決の難しい問題です。市場のニーズが変化する中で、人材をすぐに育成するのは容易ではありません。そのため、大学としては今後のトレンドを見越し、戦略的な計画を立て、将来の需要に対応できる人材を輩出する必要があります。
パイロード教授: 新しい専攻を提案すると、「その分野で本当に就職先があるのか」「卒業生はどんな仕事をするのか」といった声が上がることもあります。しかし、変化を待ってから動くのでは遅く、チャンスを逃してしまう可能性もあります。
ナックシット助教授: 例えば、われわれは今後「自動車ソフトウェア」が将来のトレンドになりそうだと予測しており、その分野に特化した人材を輩出する計画があります。多くの企業にはまだ自動車ソフトウェアの専門家がいないため、代わりに電気、コンピュータ、機械工学で構成される複合的なチームを作っているのが現状です。
Q. 大学として民間企業から求められることは パイロード教授: 教育機関と民間企業がより密接に連携することが求められています。学生にとって卒業後の職業選択に役立つだけでなく、企業にとっては市場のニーズに応える人材の育成にもつながります。工学部のカリキュラムは広範囲で、医学部のように卒業後に決まった進路があるわけではありません。そこで、私たち教員は基礎知識を教えるだけでなく、分野への関心を高める機会を提供しています。例えば民間企業を招き、学生に新たなキャリアの道を示すセミナーの開催などです。
ナックシット助教授: 教室で勉強するだけでなく、実体験が必要です。当校では、学生が興味のある科目を深く学び、卒業後に自分の興味や将来の進路を見つけられるよう、プロジェクト型の学習や専門性のある科目を取り入れています。
パイロード教授: また、3年終了後・4年前期に科目として実施するインターンシップ制度もあります。受け入れ先企業は、学部の関連企業だけでなく学生が自ら応募する企業や、また、海外へのインターンシップに行く学生もいます。
ナックシット助教授: インターンシップに加え、タイ自動車技術協会が主催する「TSAE Auto Challenge Student Formula」という課外活動もあり、学生たちの自分探しにもつながっています。この活動では、設計、作成、競技の段階、川上から川下まで、学生が実際に学んで実行することができます。現在、チュラーロンコーン大学のチームを含め、全国で約30チームが参加しています。
Q. 日本企業との連携機会は ナックシット助教授: 日本企業は国内外で人手不足に直面していますが、この課題を解決するために、タイの若者が大きな役割を果たす可能性があると考えています。具体的には、タイの若者が日本で実際の仕事を学び、その経験をタイの拠点で活かすという形です。これにより、日本の企業文化とタイのコンテクストを深く理解できる人材が育成されます。また、インターンシッププログラムを通じて、学生が日本の企業文化を学びながら実際の業務に触れることも効果的だと考えます。
パイロード教授: もう一つの方法は、大学との共同研究や、企業が学生の授業に参加する形です。具体的には、日本企業が学生に課題を出し、企業の担当者が教員と一緒に指導を行うという形です。このような協力はこれまで日本企業と行った例がなく、関心が高まっています。
>>本連載「日タイ経済共創ビジョン」の記事一覧
– Interviewee Profile –
Prof. Dr. Pairod Singhatanadgid
パイロード・シンハタナッドキッド教授
チュラーロンコーン大学機械工学科卒業。米国ワシントン大学機械工学修士号・博士号取得。現在、チュラーロンコーン大学工学部機械工学科長を務める。
Asst. Prof. Dr. Nuksit Noomwongs
ナックシット・ヌムウォン助教授
チュラーロンコーン大学機械工学科(自動車工学専攻)卒業。東京農工大学工学部機械システム工学科修士・博士課程修了。現在はチュラーロンコーン大学工学部機械工学科の助教授。