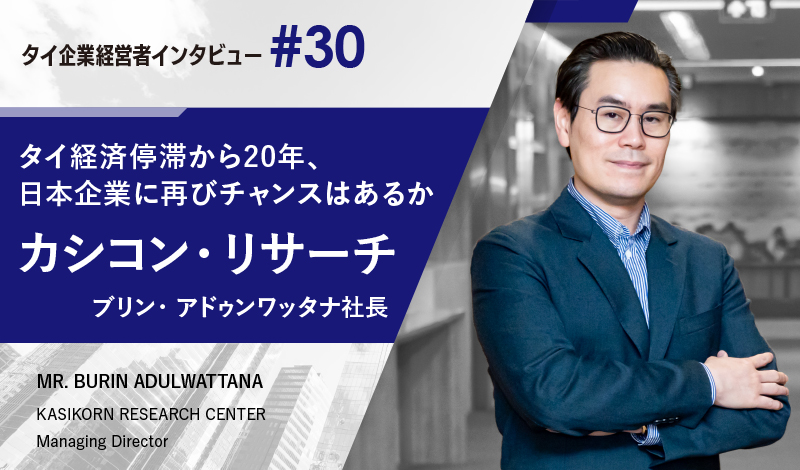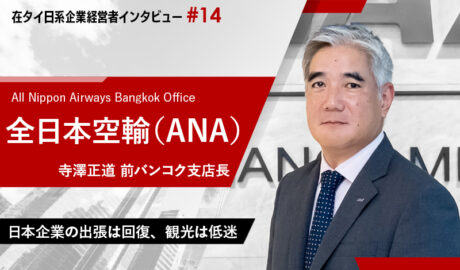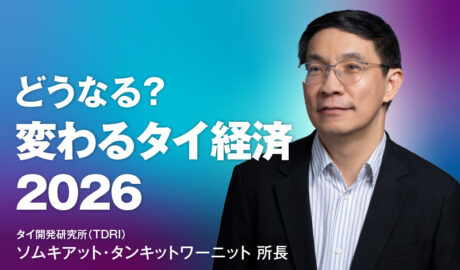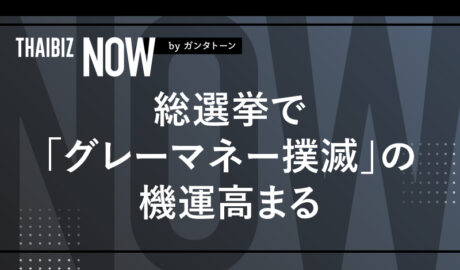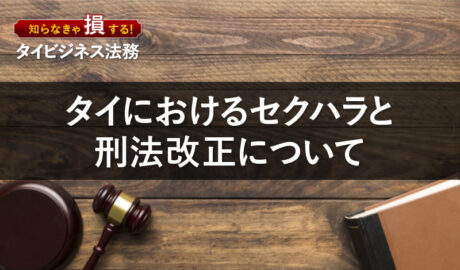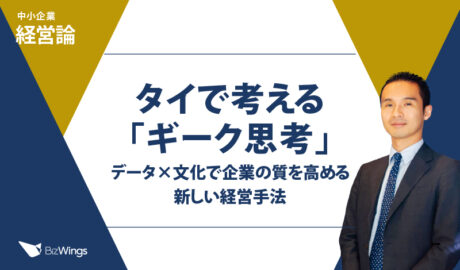最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中
タイ経済停滞から20年、日本企業に再びチャンスはあるか ~カシコン・リサーチのブリン・アドゥンワッタナ社長インタビュー
公開日 2025.11.13
かつてタイは「東南アジアの奇跡」と呼ばれた国の一つだ。1990年代、タイは短期間で高所得国へと発展する可能性を秘めた国として注目を集め、経済は飛躍的な成長を遂げた。日本、米国、欧州、台湾などからの直接投資が相次ぎ、製造業を中心に多くの企業がタイに進出した。とりわけ1988年には、日本企業の生産拠点移転の波を背景に、国内総生産(GDP)成長率が13.3%という過去最高を記録した。
しかし、1997年のアジア通貨危機以降、タイ経済の成長率はかつての水準に戻ることはなかった。現在では、国内産業の遅れや生産性の伸び悩みといった構造的課題が指摘されており、高所得国への道のりはいまだ遠い。
今回はカシコン・リサーチのマネージングディレクター兼チーフエコノミストのブリン・アドゥンワッタナ氏にインタビューし、タイ経済の現状と課題、日本企業にとっての投資機会などについて話を聞いた。
 カシコン・リサーチのブリン社長(左)、mediatorのガンタトーンCEO(右)
カシコン・リサーチのブリン社長(左)、mediatorのガンタトーンCEO(右)
タイ経済の成長回復への期待は
Q. カシコン・リサーチは、どのような役割を担っているか
ブリン社長:第一の役割は、親会社であるカシコン銀行の事業基盤を強化することだ。各産業分野の分析を通じて、銀行の顧客企業をサポートしている。さらに、国の政策研究も担っており、国家経済全体の健全な発展を促す重要な役割として位置づけられている。
タイ経済が健全でなければ銀行業も持続的に成長することはできない。そのため、カシコン・リサーチは単なる統計や理論分析ではなく、政府および社会に対して「タイ経済は減速し、景気後退のリスクが高まっている」という警告を社会に知らせている。
今のままではタイが世界経済の潮流から取り残される懸念があるが、いま改革を起こせば、タイ経済は再び成長軌道に乗り、プレゼンスを取り戻す潜在力が十分にあると信じている。
タイ政府に問われる、抜本的改革の実施能力
Q. 現在のタイ経済、強みと主な制約は
ブリン社長: ASEANの中心に位置する地理的特長や、自動車産業を中心とする堅固な産業基盤など、タイは依然として多くの優位性を有する。自動車産業は、タイが「アジアのデトロイト」と呼ばれる契機となった主要分野であり、現在も製造業の中核となっている。また、観光業および医療サービス産業も依然としてタイ経済を支える産業であり、さらなる成長余地も見込まれる。
一方、タイ経済は構造的課題によって成長の鈍化が続いている。政府による各種政策は短期的な対策に留まっており、高齢化の進行や、産業ニーズに合致しない教育システムに起因する高度技能人材の不足といった根本的課題に十分に対応できているとは言えない。輸出面においても、自由貿易協定(FTA)を締結している国の数がベトナムやマレーシアなどの近隣諸国ほど多くなく、輸出競争において劣勢に立たされている。
タイにとって重要な自動車産業においては、世界的に電気自動車(EV)への転換が進んでいる。タイでも外国企業が急速にEVへの投資を推進している。一方、技術水準およびインフラ整備が追いついていない。さらに、労働コストは相対的に高く、近隣諸国からの労働力に依存する構造が継続して見られるが、高度人材の育成は依然として課題である。
これらの問題は、労働市場、教育システム、規制環境といった各分野における抜本的改革の実施能力が政府に問われていることを示している。改革が進展しなければ、現在約2.5%にとどまる経済の潜在成長率はさらに低下し、長期的には国際競争力の喪失を招くおそれがある。
農業・食品分野における、日タイ連携の展望
Q. 農業および食品分野において、タイと日本の連携にはどのような可能性があるか
ブリン社長: タイの農業は、豊かな生物多様性を強みとする一方で、依然として一次産品のまま輸出することが多く、付加価値化が進んでいないことが課題だ。今後、研究開発を通じて多様な形で高付加価値化を図る必要があるだろう。例えば、ココナッツを原料とした化粧品、サプリメント、漢方薬への応用などが考えられる。
こうした高付加価値製品づくりに、日本の研究機関や企業パートナーが参画し、科学的に品質を向上できれば、国際市場での信頼性とブランド価値を一気に高めることが可能だろう
また、主要農作物である米、キャッサバ、サトウキビの生産農家の多くは、低い収益性に苦しんでいる。政府や民間が研究開発を強化し、バリューチェーン全体を巻き込んだ加工モデルを確立できれば、輸出依存から脱却し、より持続的な所得構造を構築できるだろう。
例えば、サトウキビの搾りかすや茎の残さは、通常は焼却され、微小粒子状物資(PM2.5)の原因となる。このような農業残さはバイオ燃料として再利用することが可能だ。日本はこの分野において高度な技術とノウハウを有しており、こうした日タイ連携が実現すれば、環境汚染の軽減だけでなく、タイ農村経済に新たな価値を創出し、タイ人農家の貧困の循環を断ち切る契機となりうると考える。
さらに、地球の環境変化は、カーボンクレジット制度の整備やグリーン経済の推進など、タイにとって新たな経済モデルを構築する契機にもなりうる。スマート農業や有機農業への転換が、持続的な所得を生み出し、タイがグローバル・サプライチェーンの新たな位置づけを確立する鍵となるだろう。

タイ農業のジレンマ、構造転換の遅れが生む停滞
Q. タイの農業の現場にはどのような課題があるか
ブリン社長: スマート農業への移行の停滞や、化学肥料の過剰使用による土壌劣化などの問題がある。持続可能な解決策としては、有機農業の推進や森林再生によるカーボンクレジット収入の創出が挙げられる。例えば、地域レベルでのファンド(村落基金など)を設立し、森林保全に取り組む農家に報酬を与える仕組みを構築すれば、環境保全と経済的安定の両立が可能となるだろう。
しかし現実には、政治的要因や制度改革の遅れもあって、タイの農家は依然として政府補助金への依存から抜け出せていない。その結果、採算の取れない生業から脱却できず、非効率な構造が固定化している。こうした状況が続く限り、根本的な問題解決には至らないだろう。
「生産拠点」から「中国の迂回拠点」の恐れ
Q. 米国による対中関税措置は、タイ経済にどのような影響を及ぼしているか
ブリン社長: 世界貿易は転換点に立たされている。従来の自由貿易体制はもはや元に戻らない可能性が高く、多くの投資家が「米国は依然として信頼できる貿易パートナーなのか」と疑問を抱いている。
また、「チャイナ・プラスワン」政策の流れに沿ってタイへ生産拠点を移した企業も少なくない。しかし近年、タイが中国のトランスシップメント拠点として利用されているとの見方が強まり、そうでない企業までが二次的な影響を受けるリスクが指摘されており、米国などから現地調達率の引き上げを求められる可能性もある。一方、タイヤ産業のように国内で原材料を確保できる分野は引き続き競争優位を保っていると言える。
成熟化する国内市場、次の一手は
Q. タイの大手企業の動向と、新たなビジネス機会についてどのように見ているか
ブリン社長: タイ証券取引所(SET)に上場する大手企業の多くは、エネルギー、小売、不動産といった従来型の事業分野に依存しており、これらの市場はすでに飽和の段階に差しかかっている。このため、多くの企業が中国、ベトナム、インドネシアなど海外への投資拡大に踏み出しており、国内市場の展望はかつてほど明るくはない。また、信用供与の伸び悩みや融資審査の厳格化もあり、国内の資金循環が鈍化している。
一方、これが必ずしも成長の終わりを意味するわけではない。優秀な人材の誘致と税制構造の見直しを戦略的に進めることができれば、タイは新たなポテンシャルを開拓できる可能性があるだろう。例えば、多国籍企業のバックオフィス機能や地域統括拠点としての役割を担うことが考えられる。
現行の個人所得税率35%は外資系企業の進出を阻む大きな障壁だ。もし個人所得税率を約20%程度まで引き下げ、さらに行政・規制手続きの透明性を高めることができれば、高度人材や経営層の誘致が現実味を帯びてくる。そうすれば、タイのさらなる経済発展が期待できるだろう。

「開かれた商業都市国家」、タイが取り戻すべき原点
Q. タイは今後、どのような立ち位置を取るべきか
ブリン社長: 現在のタイの政策には、民族主義的で内向きの色合いがやや強い傾向が見られる。だが、タイ経済の再活性化には、かつての「開かれた商業都市国家(Open Trading City)」としての姿を取り戻す必要がある。この概念はアユタヤ時代、特にナライ大王の治世(17世紀)にまで遡る。当時のシャム(タイの旧国名)は、多くの欧州人や外国人専門人材を受け入れ、その知識と技術を国づくりに活かしていた。
今日のタイにも同様に、世界中から有能な人材を呼び込み、共に国を築くという発想が求められるだろう。シンガポールやアメリカのように、「開放・透明性・競争・専門性」を基本原則とすべきである。具体的には、長期滞在ビザやワークパーミットの発給制度を再整備し、外国人が安心して生活・投資できる環境をつくること、さらに高度人材に対しては永住権・国籍の付与を検討することも有効だろう。
また、外国人事業法を見直し、国籍にとらわれず公平な競争環境を整備すること、国営企業の規模を適正化することも重要である。
土地・都市政策の面でも改革が求められる。遊休地に対しては税制改革を通じて開発を促進し、土地の有効活用を図ることが重要だ。また自動車税制においても、排ガスの多い旧車への課税を強化することで、都市の生活環境と投資魅力度の向上を図るべきである。さらに、タイでは公務員が労働人口の約10%を占めており、行政組織のスリム化も避けて通れない。成果に応じたパフォーマンス・ベース評価を導入し、優秀な人材を行政組織に引き留めることで、より機動的で信頼性の高い行政を実現できるだろう。
タイの改革を阻む最大のボトルネック
Q. 国家改革において、タイの官僚組織や公的部門はどのような役割を果たしているか
ブリン社長: 行政官僚が本気で実行に移さなければ、政策は形だけで終わってしまう。 改革の鍵を握るのは、デジタル化による行政プロセスの透明化である。
具体的には、E-Government(電子政府)を通じて、許認可の取得から予算執行、調達プロセスに至るまでを一貫してデジタル化し、外部から検証可能な仕組みを構築することが不可欠だ。こうして汚職や癒着の温床を取り除くことができれば、行政の効率性と信頼性は高まるだろう。
参考になるのは、エストニアの事例である。同国では電子政府を国家レベルで導入した結果、行政手続きが迅速化し、透明性が飛躍的に向上、官民の利益相反が大幅に減少した。タイも、行政のデジタル化を軸に据えた改革を本格的に進めることができれば、持続可能で公正な統治体制への転換が可能になると考えられる。
日本の品質は最大の強み、必要なのは「リスクを取る勇気」
Q. 日本企業が今後もプレゼンスを維持するためには、どのような変化が必要か
ブリン社長:日本は依然として「品質の高さ」で世界から高い評価を受けている国である。一方で、保守的な意思決定文化が根強く、行動の遅れや変化への対応の遅さが課題だ。今後も国際的な信頼を維持していくためには、日本の強みである品質へのこだわりを維持しつつ、マインドセットを「保守」から「挑戦・実験」へと転換することが求められるだろう。
かつて日本は世界をリードする技術大国であった。しかし、1991年、日本のバブル経済の崩壊以降、リスク回避の姿勢が強まり、新たなイノベーションの芽を摘んでしまった側面がある。それに対し、中国は「Fail Fast, Try Often(失敗を恐れず、素早く試す)」という考え方を実践し、直感を重視した意思決定で急速に成長してきた。
日本には依然として確かな基盤技術と研究力が存在する。もし、リスクを恐れず、市場への投入スピードを高め、実践の中で技術を磨く姿勢を取り戻すことができれば、日本は再び世界の舞台で技術革新を牽引するリーダーとしての地位を取り戻す可能性を秘めている。
自動車産業から医療機器産業にシフトできる可能性
Q. タイが今後、より魅力的な投資先となるためには何が必要か
ブリン社長:タイの最大の強みは観光産業だが、これまでは短期滞在型や娯楽中心の旅行サービスに偏っていた傾向がある。タイには医療・ウェルネス分野における高いポテンシャルがあり、健康ツーリズム、医療ツーリズム、退職後の移住先へと発展させられる余地は大きい。長期滞在や療養を求める高齢層にとって極めて魅力的な国となりうるだろう。
さらに、タイにはすでに確立された自動車部品・電子部品のサプライチェーン基盤が存在する。企業はこうした基盤を活かして、医療機器産業および医療工学産業へ進出することができるだろう。これらの分野は世界的に需要が拡大しており、日本、米国、ドイツなどの外資企業と連携することで、国際的な品質基準の確立と、タイ製品のブランド価値向上が期待できる。

Interviewee Profile
ブリン・アドゥンワッタナ氏(Burin Adulwattana)
英国ケンブリッジ大学にて数学と経済学の学士号および修士号を取得。タイ中央銀行、バンコク銀行といった金融セクターでの経験を経て、2022年にカシコン銀行へ入行し、マネージング・ディレクターを務める。その後、カシコン・リサーチのチーフエコノミストを経て、現職。