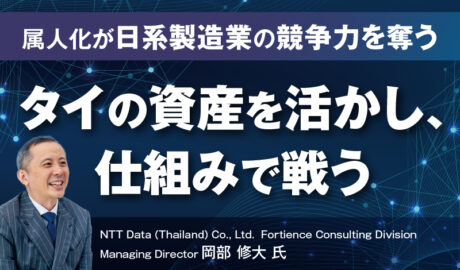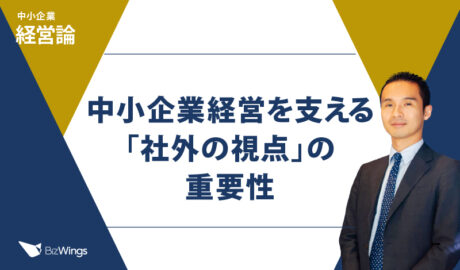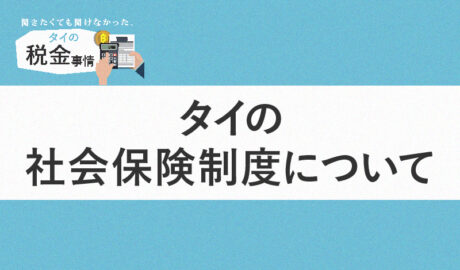最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中
総合商社の過去、現在、そして未来
公開日 2023.02.21
筆者が大学在学中で、就職のことを少しずつ考えることになった1980年代後半だっただろうか。「商社、冬の時代」という言葉が少し流行った。それから40数年、時代により浮き沈みはあるものの、大手総合商社は今でも就職人気の上位を維持し、給与水準の高さは羨望の的かもしれない。
筆者も実はある総合商社に内定をいただきながら、たまたま通信社の試験に受かり、安月給の通信社を選んでしまった。その後、経済記者を続ける中で大手総合商社のさまざまな分野の取材も経験することになり、「総合商社」というほぼ日本固有の業態に関心を持ち続けてきた。
THAIBIZニュースレターでは1月17日号以来、大手総合商社をはじめとした在タイ法人トップのインタビュー記事を掲載している。その東南アジアビジネス最前線の話を聞くことで、改めて総合商社の奥深さを再認識できる。
バフェット氏はなぜ商社株を買うのか
2020年8月、米著名投資家ウォーレン・バフェット氏率いる投資会社バークシャー・ハサウェイが、伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物産、住友商事という日本の5大商社の発行済み株式をそれぞれ5%超取得したと発表したとのニュースは株式市場だけでなく、産業界でもかなりの驚きを持って受け止められた。
バフェット氏が日本企業に投資するのは珍しいことに加え、株式市場では人気のない業種であったこともあるだろう。ただ、割安銘柄を買うバリュー投資でも知られていたバフェット氏だけに、当時割安だった日本の総合商社株を買うことに納得できる部分もあった。
そして、昨年11月にはバークシャーがこの5大商社の株をさらに買い増し、保有比率をいずれも6%超としたことが分かった。この時は、ロシア・ウクライナ戦争に伴う資源高や円安で業績が過去最高水準にあったことから違和感はなかったかもしれない。そして、バフェット氏の投資開始の頃からこれらの総合商社株は右肩上がりの展開が続いている。
バフェット氏が総合商社株を買い増し続けている真の理由はよく分からなかったが、時代に合わせて変幻自在にビジネスモデルを変えていく総合商社の底力を改めて感じている。
戦略物資などの貿易取引からスタート
このTHAIBIZニュースレターでも報じたが、タイで最も存在感の大きい日本企業であるトヨタ自動車は昨年末、進出60周年イベントを行った。東南アジアへの日系の本格進出先として最も早かった国の1つはタイであり、大企業ではタイ進出50年、60年は普通かもしれない。それでも今回の連続インタビューで総合商社のタイ進出の歴史に初めて知り、その古さ、長さを改めて実感する。例えば三井物産がバンコクに初めて出張員を配置したのが1906年だという。今から117年前だ。


そして三菱商事が最初にバンコク駐在員事務所を作ったのは1935年、88年前だった。泰国三菱商事の荻原勝一社長は今号に掲載したインタビューで、「当時はコメや天然ゴムなどの戦略物資を日本に輸出する拠点だった」と語っている。総合商社のビジネスが何から始まったのかが良く分かる。欧州各国が大海原に乗り出し、17世紀には英国やオランダが東インド会社を作って世界貿易を支配、植民地を広げ、世界経済を牛耳るようになったことを知り、明治維新以後、日本もそこに追いつこうとし、その先兵を務めたのが総合商社なのだろう。
タイでも総合商社各社の伝統的事業はやはり貿易取引だが、そのほかの主力事業はさまざまだ。例えば、石油・天然ガス開発(三井物産)、電力などインフラ事業(丸紅)、工業団地開発(住友商事)、そして三菱商事は自動車販売などだ。
特に、いすゞ自動車がなぜタイでの自動車販売台数でトヨタ自動車に次ぐ2位なのか、初めて赴任した当時は少し驚いたが、すぐに、三菱商事の営業マンがタイの全国津々浦々を駆け回っていすゞのトラックを売り歩いたことも大きかったと聞き、納得させられた。
現地化は「道半ば」
大手総合商社のタイ現地法人トップインタビューで分かったのは各社にそれぞれの特徴はあるものの、基底にはほぼ似たマインドがあることだ。各社それぞれの企業理念、社是を大事にし、本社から派遣された駐在員は現地社会に溶け込むために、現地の企業や国民の信頼を得る努力を積み重ねてきた。
特に東南アジアでは英語だけではなく現地語を習得する必要もあり、タイでは現地語学研修も実践している会社も多い。一方で、ローカルスタッフの登用が課題となっている。
英語圏なら日系企業の現地法人でもローカルスタッフがトップを務めることもあるだろう。しかし、タイでは極めて少なく、銀行や総合商社では皆無だ。それはやはりタイ語という特殊言語ゆえか。


「本社との連携でボトルネックがある。ローカルスタッフの幹部を育てても、本社側では結局、日本語の世界になり、コミュニケーションが十分に取れないこともある」(福田康・タイ住友商事社長)と指摘されている。
意外だったのは、商社マンと言えば、ほぼ全員、英語が堪能だと思われ、社内言語を英語にしても良さそうだが、まだそうなってはいないということか。以前、社内公用語を英語にしますという日本企業も出てきたが、その後、どの程度定着しているかは知らない。いずれにせよ、「現地化は道半ば」(加藤丈雄・泰国三井物産社長)のようだ。
一方、タイ人側の問題としては海外を志向する人が少ないという。「タイ人も自ら手を挙げて海外に出て行ってほしい」(日高和郎・丸紅泰国会社社長)という声も聞かれた。さらに、かつてはタイの若者は留学先に日本を選ぶ人が多かったが、最近は欧米留学組も増え、「帰ってきたら日本企業でなくても良いことになる」(福田氏)という状況にもなりつつある。
もともと、商社マンはその英語力を生かし、海外進出を試みるメーカーに引っ付いて販売など現地の事業展開の先兵となるのが最も重要な役割だっただろう。しかし、特に大手製造業では英語が堪能な社員も増え、商社マンに頼らなくても良くなり、「商社が誰かの間に挟まる時代はもう終わりだ」(日高氏)というのも既にコンセンサスだろう。このため各社、新しいビジネスモデルをいろいろ模索し続けている。
ビジネスモデルの変容
例えば丸紅では、やはり貿易取引から始まったものの、「日系企業が現地生産に切り替える中で商社も一部出資させてもらう形が1990年ごろまでは主流だった。しかし、その後、当社は出資を引き揚げた。マイノリティー出資では発言権がないからだ」(日高氏)という。
今や、合弁事業はほとんどなくなる一方、独自で資金を投入しリスクを取る事業を展開している。商社は貿易取引会社から一種の投資会社に変容しつつある。そしてその投資対象は各社、各国でさまざまだ。もちろん総合商社が昔から得意としていた資源などのバルク商売は継続しており、今回のロシアとウクライナ戦争による、エネルギー資源・穀物価格の高騰の恩恵も得られるとの見通しから、バフェット氏は投資を継続しているのかもしれない。


一方で、こうした川上ビジネスから川下ビジネスを強化している総合商社も増えており、伊藤忠商事がその典型とされる。さらに世界のビジネスが脱炭素、持続可能性重視に傾き、タイではバイオ・循環型・グリーン(BCG)経済モデルが提唱される中で、「タイは強みであるバイオマス資源と農業を活かしていくべきだ」(加藤氏)といった方向性を志向する動きも広がりそうだ。
さらに、三菱商事のように「会社の長期戦略の1つは地域創生だ。地域の産業を振興する中で、そこで生まれた価値を共有していく」(荻原氏)方向も出始めており、実際にコンケン大学と連携した取り組みを進めている。資源分野などでのバルクビジネスから、川下事業あるいは、地道な地域創生的な事業へ徐々にシフトすることで総合商社の高収益を持続できるのか興味深い。