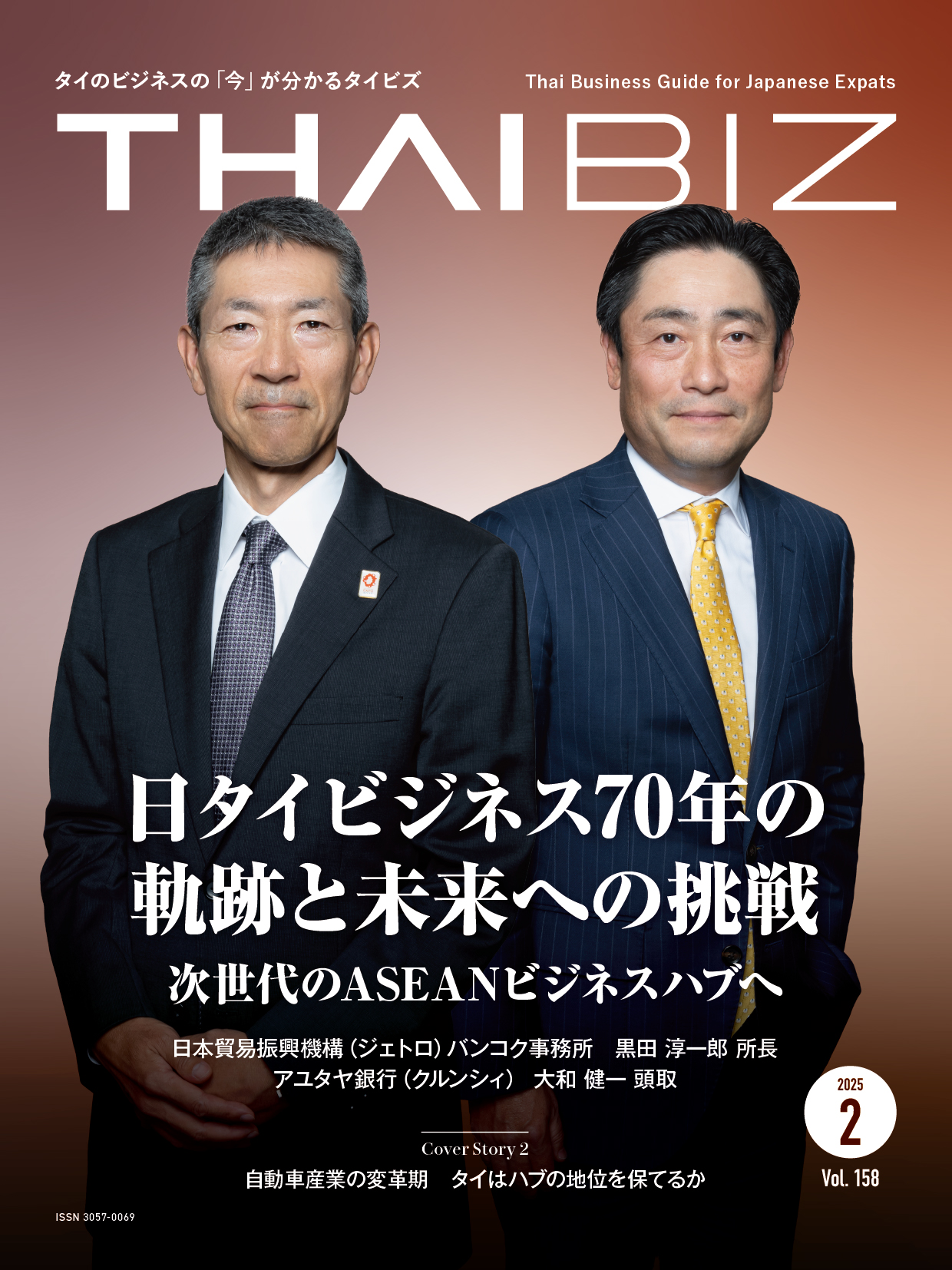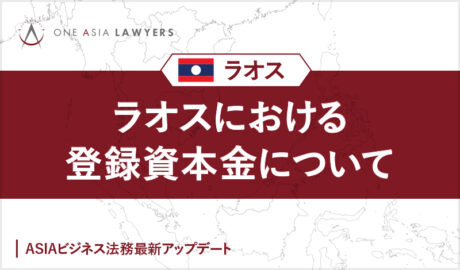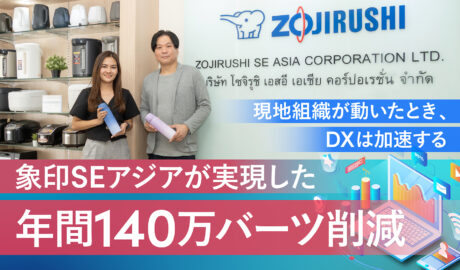社員の役割に合わせた活用方法で組織力の底上げも実現できる – YAMASA ASIA OCEANIA CO., LTD.
公開日 2025.02.10
※2025年4月1日よりTJRI法人会員はTHAIBIZ法人会員に名称変更となりました。
ようやくタイ企業との接点が持てたとしても、「そこから先の意思決定権者との本格交渉までたどり着かない」という悩ましいケースはないでしょうか。ヤマサアジアオセアニア株式会社の鹿沼篤志社長は、TJRI 法人会員の入会理由として「決定権を持つトップ層との接点が欲しかった」と回答。
さらに、ビジネス講座やタイ企業訪問イベントへの社員の参加が、組織力の底上げにも役立っているといいます。TJRI 法人サービスを通じた組織成長について、鹿沼社長、北野経理総務部長、栂原営業マネジャーに話を伺いました。

YAMASA ASIA OCEANIA CO., LTD.
アジア・オセアニア地域を対象に、日本産醤油・調味料の輸入販売、タイ産醤油・調味料の開発・販売、オーダーメイド商品の開発・販売を手がける。
醤油・調味料の輸入、製造、販売事業を展開
Q. タイでの事業展開についてお聞かせください
鹿沼氏:2008年に、タイ大手調味料製造メーカーとの合弁会社「ヤマサタイランド株式会社」を設立したことが、タイ進出の始まりでした。2016年のBOI 規則変更に伴い100%独資での卸事業展開が可能になったことで、現在のヤマサアジアオセアニア株式会社となりました。その後も、同社に製造を委託しており、技術者を出向させるなど品質を担保しながら、関係性は続いています。
当社は、アジアおよびオセアニアを対象地域として、①日本産醤油・調味料の輸入販売、②タイ産醤油・調味料の開発・販売、③顧客ニーズを日本と同レベルで再現可能な特注商品の開発・販売の3事業を展開しています。
醤油をはじめ、めんつゆ、たれ、ソース、ドレッシングなどをヤマサの商品として製造販売するほか、オーダーメイドで調味料を作ることで、お客様のニーズに寄り添ったサポートをさせていただいています。タイに拠点を置く当社は、ハラル対応の製品を製造しインドネシアやマレーシアなど周辺国の調味料メーカー向けに輸出するなど、アジア・オセアニアの中でもハブ的な立ち位置にいます。
担当者ベースでは「繋がりの継続性」に課題
Q. 御社が感じられていた課題と、TJRIご利用のきっかけについて教えてください
鹿沼氏:タイ企業の購買担当と繋がることができても、担当者クラスのため「数ヶ月後にコンタクトしたら、担当者が変更していた」というケースも多く、繋がりの継続性に課題がありました。特にタイではトップダウンの構造が根強いため、決定権を持つトップ層と接点を持ちたい気持ちが強く、それが叶うTJRI 法人会員サービスに入会しました。
きっかけは、Mediator主催の「タイ人を知る」と題する講座を受講したことです。歴史や文化の側面からタイ人の考え方の傾向などが学べたため、非常に納得感のある内容でした。ローカルスタッフとの関係性構築や経営活動にも、大きく役立てることができました。TJRIにはタイ企業と接点を持てる機会以外にも、こうしたビジネス講座を無料で受講できるメリットもあり、入会後は他の日本人社員やタイ人社員にも積極的に受講してもらっています。
社員の役割にあった活用方法で、組織力も底上げできる
Q. 実際にTJRIを利用された感想をお聞かせください
北野氏:現在、前職やタイでの経験を活かしながらインドネシア法人の立上げもサポートしており、経理人事総務等バックオフィス分野での会社基盤を整えるスペシャリストを目指して日々精進しています。タイビジネスを基礎から学べる「ビジネス講座」は毎年受講し、会計・労務・人事についての知識をアップデートする機会として重宝しています。最近では、「なぜタイ人は日系企業を“ 選ぶ” のか?」第二回セミナーにも参加し、現地化に向けた人事改革の事例から多くの学びを得ることができました。
栂原氏:私は、農業・食品最大手チャロン・ポカパン・フーズ(CPF)のR&Dセンター視察イベントに参加した時、サプライヤーとして繋がりを持つ当社でも普段は入り込めない部分まで視察ができたことに感銘を受けました。他参加者からの質問も後を絶たず、皆さんの高い関心度が伺えました。
参加後は、イベントで得られた内容を社内でローカルメンバーに展開し、その後の営業活動にも役立てています。CPFと当社で醤油の勉強会を行った際に「視察イベントに来ていましたね」と声をかけてもらい、スタートから雰囲気が和んだこともありました。既に取引のある企業の訪問イベントにも、確実な参加メリットがあると感じた瞬間でした。
鹿沼氏:私が参加したパンヤピワット経営大学(PIM)訪問イベントでは、CP Allが即戦力となる人材の育成を行う企業大学を運営している事実を初めて知り、強い刺激を受けたことを覚えています。空いた枠を経験者採用で補完する採用方法に限界を感じ、新卒採用の導入などタイ人社員を中心とした組織づくりに注力し始めた時期だったからです。タイ企業の人材育成に対する熱量を感じたとともに、採用や育成の観点で大変参考になりました。
 TJRIミッション:パンヤピワット経営大学(PIM)訪問イベントの様子
TJRIミッション:パンヤピワット経営大学(PIM)訪問イベントの様子
その他、タイ企業の経営幹部が課題やニーズを解説するオープン・イノベーション・トークなどにも参加し、タイ企業の経営層と接点が持てたことや、普段関わることのない他業界の日系企業との繋がりが生まれたことも大きな成果だと思います。北野や栂原の言葉にもある通り、私だけではなく社員それぞれが自分の役割に合った活用をすることで、組織力の底上げにも繋がっていると感じます。
Q. 最後に、タイでの事業展望をお聞かせください
鹿沼氏:アジアのハブ機能を発揮して、ヤマサの立ち位置を確立・拡大していくことが目標です。日本品質ブランドに必要性を感じてもらうためにも、タイの料理人のレベル向上に向けた取り組み等も積極的に行っています。タイでは、現在のパートナー工場では対応不可能な部分を補完できるような、新たなパートナーも模索しています。引き続きローカルとの関係性が重要な土台となりますので、TJRIを組織全体でうまく活用し、さらなる事業発展に繋げていきたいと考えています。
※2025年4月1日よりTJRI法人会員はTHAIBIZ法人会員に名称変更となりました。