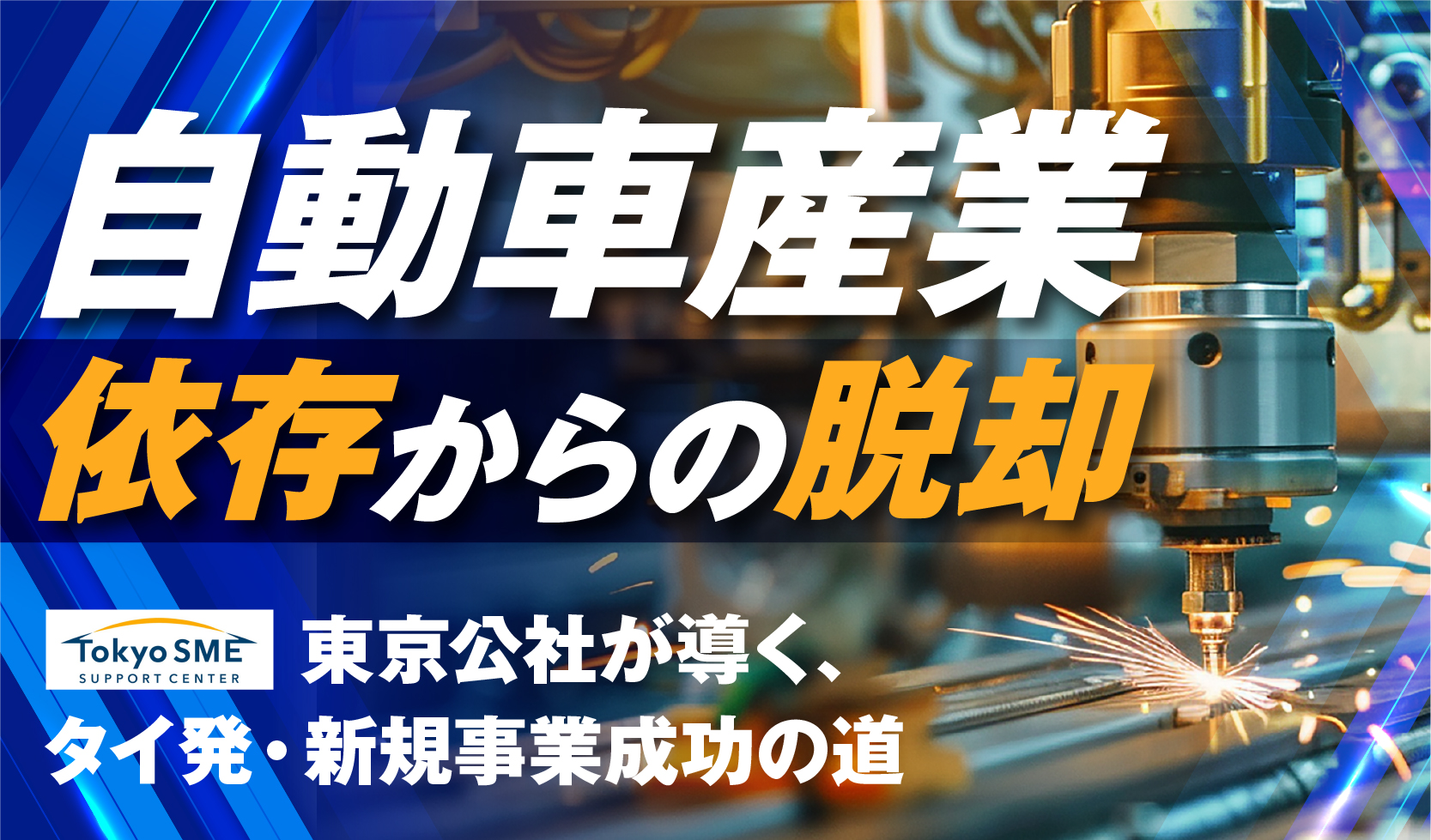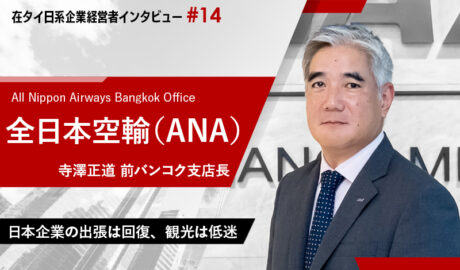最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中
自動車産業依存からの脱却―東京公社が導く、タイ発・新規事業成功の道
公開日 2025.11.25 Sponsored
タイでは長年にわたり、自動車産業が日系企業の主力分野として発展してきた。しかし近年、タイ経済の停滞や、EVシフトがもたらすサプライチェーン再編の波を受け、日系企業は次の一手を模索せざるを得ない局面に立たされている。
一方で、同国の豊富な資源を活かし、バイオや再生可能エネルギーといった新分野で事業を立ち上げ、成果を上げつつある企業も現れ始めた。
本記事では、東京都中小企業振興公社(以下、東京公社)事業戦略部 販路・海外展開支援課の山本康博課長にインタビューを実施。タイにおける新規事業の事例を通じて、日系企業が自動車産業依存から脱却し、新たな分野で成功するためのヒントを探る。
自動車産業の転換期に求められる「両利きの経営」 タイでは、バンコクを中心とした約6県に日系企業が高密度に集積している。この集積度の高さは世界的にも稀であり、長年にわたって培われてきた強固なサプライチェーンは、同国の産業基盤を支える大きな強みとなっている。
一方で近年は、「中所得国の罠」による経済の停滞や急速なEV化がもたらすサプライチェーンの再編により、自動車産業にかつての勢いは見られなくなっている。
こうした転換期を乗り越える鍵として、山本氏は「両利きの経営」という考え方を挙げる。「競争が激化し、プレイヤーが淘汰される中、これまでのやり方を続けているだけでは生き残れない時代に入っている」と警鐘を鳴らし、「企業が持続的に成長するためには、既存事業を深掘りする“知の深化”と、新たな分野を開拓する“知の探索”の双方が欠かせない」と強調する。
タイの資源と現地協業で広がるビジネスチャンス もっとも、新規事業の種を見つけることは決して容易ではない。仮に見つけたとしても、事業として立ち上げるには資金面での課題も伴う。
山本氏は「資金力のある大手企業と異なり、中小企業にとって新たな挑戦はハードルが高いかもしれない。しかし、そうした時こそ東京公社をはじめ、国や自治体が実施する補助金制度などを積極的に活用して“知の探索”を進めてほしい」と呼びかける。
さらに同氏は、「タイには豊富な資源があり、そこには多くのビジネスチャンスが眠っている。現地の大学や地場企業と手を組むことで、事業の可能性はさらに広がるだろう」と、タイ市場の潜在力の大きさに期待を寄せる。
東京公社 事業戦略部 販路・海外展開支援課 山本康博課長
タイでの日タイ企業マッチング実績は5,000件以上 東京公社タイ事務所は、2015年の設立以来10年間にわたり、タイ工業省などと連携して、日本の中小企業を対象に経営支援やビジネスマッチング、ネットワーキングなど幅広いサポートを提供してきた。
なかでも注力しているのが、専門知識を持つアドバイザーが架け橋となって実施している日タイ企業間のビジネスマッチングだ。企業のニーズに応じて、市場調査や候補企業リストの提供、個別マッチングなども行っており、これまでのマッチング実績は5,000件を超える。
さらに、タイの食品メーカーの課題を起点に日本企業のソリューションを提供する「食ビジネスマッチング」にも取り組んでおり、日本のパッケージング技術や食材裁断機械などがタイ企業に導入された事例も複数あるという。
こうした現地密着型の支援を通じて東京公社には、「両利きの経営」を理論ではなく実践で体現している企業の事例が蓄積されている。その一つが、タイ大手製糖会社のMitr Phol Sugar Corp., Ltd.(以下、ミトポン)である。
廃棄していた残さを活用、ミトポンの新たな挑戦 ミトポンは、従来の製糖事業の枠を超えた新たな分野に挑戦し続け、新境地を切り拓いている。同グループはサトウキビに新たな価値を見出し、2019年には化学技術省(MOST)の協力のもと、サトウキビ由来の天然化粧品「Chuen Jai by Mitr Phol」を開発。高品質な天然砂糖からつくられる同製品には、乳酸などの成分が豊富に含まれ、肌を活性化させ、潤いと輝きをもたらす効果があるという。
さらに、サトウキビから砂糖を製造する過程で生じる残さを有効活用し、バイオマスプラスチックや生分解性プラスチック、バイオエタノールなどといったバイオベース製品関連事業の拡大や、再生可能エネルギー開発も推進中だ。
同社は2022年、丸紅株式会社が100%出資する丸紅泰国会社と戦略的協業に関する覚書を締結。丸紅グループの知見やネットワークと、ミトポンのアグリビジネス分野における強みを融合させ、これまで処理コストをかけて廃棄していた残さを再資源化することで、新たな事業創出への道を開拓したのだ。
現地に根付いた研究開発で新事業を創出するダイセル 日本企業の好事例もある。エンジニアリングプラスチック事業やマテリアル事業などを展開する株式会社ダイセル(以下、ダイセル)は、もともとエアバッグをはじめとする自動車部品を主に生産していた。しかし現在では、固定観念を打ち破る新しい技術を軸に、新事業を次々と立ち上げている。主な研究開発の舞台は、日本ではなくタイだという。
その一例が、非可食バイオマスを原料とし海洋生分解性を備えたバイオマスプラスチックや、エアバッグのガス発生器製造で培った技術を応用した、ガス式の針なし医薬品・ワクチン用注入器の開発である。後者の製品は、高圧で医薬品またはワクチンを押し出すことで、注射針の使用なく皮下への投与を可能とする、これまでの常識を覆す注入器だ。ダイセルは今年11月、同製品の医療機器製造販売承認を取得した。
山本氏は「同社の新規事業を牽引するキーパーソンは、2度のタイ赴任経験がある山田良平執行役員だ。彼は日本への帰任後も、チュラーロンコーン大学をはじめとする教育機関と連携し、タイの学生や教授と共同開発を推進している」と説明。「同社は、タイの豊富な資源や優秀な人材と自社技術を組み合わせることで革新的な事業を継続的に生み出しており、極めて優れた事例と言えるだろう」と評価する。
タイ工業省副事務次官も来日、海外展開シンポジウムを開催 東京公社は12月12日(金)、海外展開を検討する都内中小企業や、すでにタイで事業を展開している企業を対象に、「海外展開シンポジウム」をハイブリッド形式で開催する。同シンポジウムのために来日予定のタイ工業省のパサコーン・チャイラット副事務次官をはじめ、ミトポンの新規事業担当者やダイセルの山田良平執行役員らが登壇予定だ。
当日は、ミトポンやダイセルがいかにして新規事業を開発し、成功へと導いたのか、その具体的なプロセスも紹介される見込み。参加者にとって、自社の技術や強みを生かして新たな事業を創出するヒントを得る貴重な機会となりそうだ。
山本氏は最後に、「産業は常に、大手企業と中小企業が重なり合うことで成り立っている。これまでにない価値を生み出す新規事業の創出は、自動車産業を超える新たな産業を形成する可能性を秘めている。それが実現すれば、中小企業の活性化にもつながるはずだ。われわれは、その一歩を後押しすることで、日タイ産業連携の新たな展開を切り拓いていきたい」と力強く語った。
シンポジウム開催概要 名称:
開催日時: 2025年12月12日(金)13:00~17:20 ※日本時間
開催形式: リアル開催とオンライン開催のハイブリッド形式
開催場所:
定員: 300名(先着順/要事前申込)参加費: 無料
対象:
◎ 山本康博 氏
2005年に東京都中小企業振興公社に入社。国内外での販路開拓支援や創業支援業務を経て、2015年から2017年にかけてタイ事務所の立ち上げを担当。2024年4月より現職。
公益財団法人 東京都中小企業振興公社
東京都が設立した中小企業支援機関として、都内中小企業の経営基盤強化と新たな事業展開を目的に、多角的な支援事業を展開。創業支援、販路開拓支援、海外展開支援など幅広い分野をカバーし、海外市場でのビジネスチャンス創出に向けて、現地事務所の設置やビジネスマッチング、展示会出展支援など実践的なサポートを行っている。
タイ事務所では、タイ工業省や現地銀行と連携しながら、経営支援、ビジネスマッチング、ネットワーキングなど、都内の中小企業に向けて現地密着型のサポートを提供している。
Web:https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/index.html