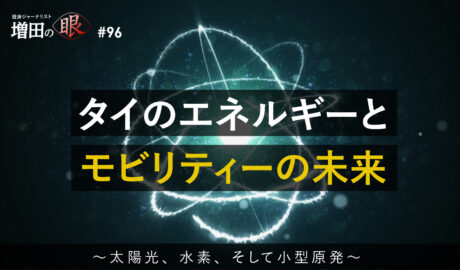駐在員必読! タイ式経営の流儀
公開日 2025.04.10
日タイのビジネス関係で多くの功績を残したカリン・サラシン氏。同氏は、タイ王室系財閥サイアム・セメント・グループ(SCG)傘下のSCGトレーディング(現SCGインターナショナル)の社長を20年間務め、タイ商工会議所(TCC)会頭やタイ政府観光庁(TAT)会長、その他さまざまな要職を歴任してきたタイ経済界の重鎮の一人だ。
現在も泰日協会(TJA)会長やタイ国トヨタ自動車(TMT)会長、TCCおよびタイ貿易委員会(BOT)の名誉会頭を兼務するなど、日タイのビジネス関係に貢献している。
今号では、同氏のこれまでの経験やタイで働く上で重要となる経営者の考え方、今後の日タイのビジネスにおける協力関係の展望などについて話を聞いた。

カリン・サラシン 氏
2001〜2021年SCGトレーディング(現SCGインターナショナル)社長。泰日協会会長、タイ国トヨタ自動車会長、タイ商工会議所およびタイ貿易委員会の名誉会頭のほか、複数の民間企業の顧問や役員を兼任し、現在もタイ経済界をリード。米ハーバード・ビジネススクール アドバンスド・マネジメント・プログラム(AMP)修了。米ノートルダム大学MBA取得。
アジア通貨危機を契機に、SCGの海外進出が加速
カリン氏は35年以上SCGで働き、重要な役割を歴任してきた。SCGが直面した大きな危機のひとつが1997年のアジア通貨危機だ。同氏は「当時はプロジェクト・マネジメントのディレクターだった。バーツの急落により、会社はドル建ての負債を多く抱えていた。事業を維持するためにキャッシュフローを生み出す必要があり、できるだけ多くの資金、特に米ドルを調達するために国際市場に参入する必要があった。われわれは欧米諸国、中東、ASEAN諸国、日本など、さまざまな国の顧客のニーズを調査し、工場のエンジニアに製品要件や価格帯などのニーズをフィードバックした」と当時を振り返る。
具体的には、まず米国市場が求めるセメントの種類や、速乾性・遅乾性といった特性の調査から始めた。新たなチャンスを見出すためには、国際市場を調査し、会社の信頼を築くことが鍵だったという。市場調査をした後、その市場に適したセメントの開発に着手した。同時に、社内のメンバーには「やればできる(Can do)」というマインドセットで、新しいことを受け入れる文化を醸成していった。
同氏は自身の経験から、「国際市場に参入するためには、品質、量、納期の3つを優先することはもちろん大切だが、それに加え、各国の顧客ニーズの違いを理解することが最も重要だ」と強調した。
アジア通貨危機をきっかけとしたグローバル市場での販路拡大で業績を回復させた後、2001年にカリン氏はSCG傘下のサイアム・セメント・トレーディング(現SCGインターナショナル)※の社長に就任した。
同社は、SCGの輸出入や、同グループ以外の農業やエネルギー関連、再生資材などの取引で国際ネットワークを拡大するために、1978年に設立された貿易会社だ。社長就任後、同氏はSCGトレーディングの拠点を8ヵ所から、アジアやオーストラリア、中東、ヨーロッパ、アフリカ、米国、南米など世界35ヵ所以上に拡大させるなど、優れた経営手腕を発揮した。また、SCGを2021年に退職した後もSCGの社長兼最高経営責任者(CEO)の顧問や複数の民間企業の役員を務め、現在もタイの経済界を牽引している。
※SCGインターナショナルは、1978年にサイアム・セメント・トレーディングとして設立され、2010年にSCGトレーディング、2019年に現在のSCGインターナショナルに社名変更。
日本企業との協力関係と実績
SCGは日本企業との関係が深く、これまで日本の各業界の名だたる企業と数多くの合弁や協業実績を持つ。同氏は、日本企業との関係構築について、「三井物産や三菱商事、伊藤忠商事、住友商事などの日本の商社とは長い間、親密な関係を築いてきた。毎年、ゴルフ大会を開催するなど、定期的に交流も深めてきた」と明かした。
一方、個人的な経験については「20年前、マレーシア向けに白色セメントを販売していた太平洋セメントに、OEM(太平洋セメントのブランド名でSCGが製品を製造すること)の提案をした。最終的に実現したのは今から1〜2年前のこと。かなり時間がかかったが、実現できたことを心から嬉しく思っている」と喜びを語った。
ビジネスを成功に導く信頼の築き方
同氏は、ビジネスを成功に導く鍵として、「最も重要なのは『信頼』を築くことだ。そして信頼の基本は、①顧客への心遣い、②約束を守ること、③リスク管理−の3つだ」と強調した上で、「顧客に対して細かいところまで気を配り、納期などの約束を守れば、信頼は高まる。一方で、為替リスクや目に見えないさまざまなリスクにも注意を払う必要がある。あらゆるリスクを低減できれば、さらに信頼を得られるだろう」と考えを述べた。
人材マネジメントの鍵は柔軟性と意見の尊重
日本人がタイで企業経営をする上で、悩みの種の一つとなっているのが、人材マネジメントである。カリン氏は人材マネジメント方法として、「まず従業員に対して公平でなければならない。特定の人を優遇せず、差別しないことが重要だ。個人の関係性や感情に左右されず、結果を重視した、客観的な判断をすることが鍵となる」と強調した。タイ人が理想とするリーダー像については、「柔軟に仕事を進めることができ、問題が発生した際にはリーダーシップを発揮して適切に対処できることが重要だ」と述べ、「特にタイでは、柔軟で順応性のある職場環境を整えることもリーダーの役目だ」と訴えた。
さらに「リーダーは、ただ命令するのではなく、直接部下の話を聞き、彼・彼女らの感情を理解して意見を尊重することも大切だ。すでに方法やアイデアを持っていたとしても、さまざまな意見に耳を傾けることで、他のより良いアプローチや可能性を探ることができるからだ」と持論を展開した。
人材育成については、「各従業員の得意分野を把握し、会社の利益にどのように貢献できるかを考えることが求められる」と指摘。その上で、「将来的に会社が必要とするスキルに対応できるよう、研修の実施や講習への参加機会の提供、ジョブローテーションなど積極的に従業員の能力開発を推進することも重要である」と付け加えた。
素早い決断と慎重な判断のバランス

優れた経営者の共通点とは何か。カリン氏は、「私の経験では、攻めと守りの判断のバランスを備えていることだ。経営者が決断できない、あるいは決断が遅い、はっきりと意思を示さないことで、新たなビジネスチャンスを逃してしまう。100%の情報が揃っていなくても、70%の情報があれば意思決定は可能かを検討しなければならない」とした上で、「その時に素早い決断によって生まれるチャンスと、ビジネスの安定性を保つための慎重な判断の見極めが鍵となる。その両方のバランスをうまく取ることで、業務の効率化が期待できるからだ」と経営者としてのマインドセットを語った。
また、「自社にとってどちらの選択がより大きな成果につながるかを基準に判断し、決断に際しては、その理由を明確に伝えることが重要だ」と強調した。
さらに、「感情に流されず、客観的な事実と収集したデータに基づいて意思決定を行うことも重要だ」とした上で、「例えば、マネジメントの品質向上には、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)の4つの業務プロセスからなる『PDCA』のフレームワークを活用することが効果的である。
しかし、その前に業務の効率性を見直す必要がある。どのプロセスが過剰に時間を要しているのかを特定し、不要な工程を省略できるかを検討する必要がある」と指摘した。また、「企画段階では、チームメンバーが参加できる環境を整え、上司だけが計画を策定するのではなく、チーム全体を巻き込んで計画を立て、各プロセスに取り組むことが重要だ」と結論づけた。
日タイ経営者ネットワークの構築に尽力
カリン氏は2017〜2021年にタイ商工会議所(TCC)の会頭を務め、現在もTCCおよび同上部組織であるタイ貿易委員会(BOT)の名誉会頭として民間企業の事業活動の支援を続けている。
TCCは、タイ国内外の政府機関や企業、学術機関と連携し、経済発展を促進している。自由貿易協定(FTA)の促進や外国直接投資(FDI)の誘致を推進する一方で、特に中小企業の成長支援や地域経済の活性化に注力している。会員数は17万4,000人(2025年3月1日時点)を超える巨大な組織で、今後数年以内に20万人まで会員を増やすという野心的な目標を掲げている。
TCCには15の部会と170以上の業界団体が所属し、各業界の専門家が在籍しているため、業界の垣根を超えた協力が可能であることも強みだ。また、政府に対しても有益な情報を提供し、経済・産業政策の策定を支援する役割も担っているという。
タイ・日本経済フォーラムをはじめ、中国やサウジアラビアへの公式訪問など、国際的なパートナーシップ強化にも取り組んでおり、タイにおける国際的なビジネスネットワークの構築やタイ人経営者との人脈づくりには欠かせない代表的な組織といえる。
さらに、TCCは、多くの在タイ日系企業が所属しているバンコク日本人商工会議所(JCC)や日系政府機関との連携も強化しており、2023年には、在タイ日本大使館とJCC、日本貿易振興機構(ジェトロ)と協力し、日タイ・トップエグゼクティブ・プログラム(J-ToP)を開始した。
同プログラムは、主にタイ人のトップエグゼクティブを対象として、日タイ間のビジネスと日本文化に関する総合的な知識の向上と参加者同士のビジネスネットワークの構築を目的としている。さまざまな分野で活躍するタイ人や日本人、一流大学の教授らによる講義だけでなく、タイ国内および日本への視察旅行などの特別プログラムを実施している。
カリン氏は、J-ToPに顧問として参画しており、自らも講義を行ったり、視察旅行プログラムに参加したりするなど、日タイのビジネス活性や事業者間のネットワークの推進において積極的に活動を続けている。
 J-ToP第1期生(2023年度)の日本視察旅行(写真:カリン氏提供)
J-ToP第1期生(2023年度)の日本視察旅行(写真:カリン氏提供)
泰日協会で日タイをつなぐ、原点は幼少期
2014年から泰日協会(TJA)の会長を務め、両国の友好協力関係にも尽力しているカリン氏。TJAは1935年に設立され、今年90周年を迎える。TJAでは、主に①経済面、②社会面、③教育面、④日本人村の保全—の4つの活動を行っている(図表1)。
 出所:TJA提供資料をもとにTHAIBIZ編集部が作成
出所:TJA提供資料をもとにTHAIBIZ編集部が作成
日タイの企業や組織の重役を兼任するカリン氏だが、そもそも日本と関わるようになったきっかけは何だったのだろうか。この問いに対して同氏は、「幼い頃、親族がデンソーやブリヂストン、大丸商事など、日本企業の株主として深く事業に関わっている姿を身近に見てきた。また、私が勤めていたSCGでは日本企業との連携事業も多く、日本人と仕事をする上での考え方を学ぶ機会も多かった」と明かした。
幼少期から日本企業が身近な存在としてあり、さらに自身も日本企業との連携事業を数多く手掛けてきた経験から、同氏がTJAをはじめ、現在も日タイ間の協力関係に深く関わっていることは、ごく自然な流れと言えるのかもしれない。
これからの日タイのビジネス関係
同氏は日タイのビジネスにおける協力の未来展望について「タイと日本は、長い友好の歴史があり、お互いに信頼関係を築いてきた。現在は、ともに高齢社会を迎えており、共通の課題も多い。こうした課題を解決するために、ヘルス&ウェルネス産業をはじめ、多くの分野でタイと日本は協力できる」と指摘した上で、「食品や農産物、医薬品などの高付加価値製品を共同開発することも、興味深いアプローチだろう。
タイには良質な原材料が多くあるが、それを発展・拡大させるには、さらなる技術や知識が必要となる。一方、日本企業はすでにノウハウや技術を持っているため、タイ企業と共同で製品開発を行い、お互いのアセットを補完できる強力なパートナーとなりうる」との見方を示した。
またエネルギー分野については、「タイでは水素の生産者と利用者のネットワークである『ハイドロジェン・タイランド・クラブ(Hydrogen Thailand Club)』を設立し、水素の普及と将来への備えを行っている。ハイドロジェン・タイランド・クラブには、タイと日本の政府機関や民間企業、学術機関が参加している。
特に廃棄物や植物由来のグリーン水素は持続可能な優れた代替エネルギー源になる可能性がある」と示唆した上で、「太陽電池ビジネスなどの太陽エネルギーをはじめとした、再生可能エネルギー分野でも、タイと日本が協力し、さらに発展させることができるだろう」と期待を示した。